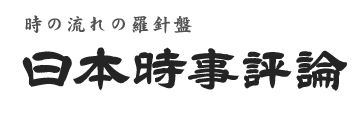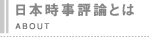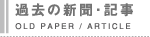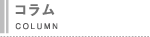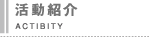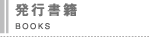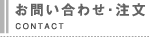毎月第1・第3金曜日発行「日本時事評論」公式ウェブサイト


過去に発行した日本時事評論のバックナンバー(PDF)と、編集便りをご覧いただけます。
日本時事評論第2078号 編集便りNo.489 2025/12/19
岐阜市では、不登校の児童生徒を増やさないため、子供一人一人を大事にし、子供の自主性を尊重した独自の教育を行っているとの情報を聞き、10月には同市立藍川東中学校、11月には同市の水川教育長に取材に行きました。自主性を尊重した教育は言葉だけ聞くと「放任」と捉えがちになりますが、取材した藍川東中学校の先生方はとにかく子供を信じ、上手くいかない時は先生方で話し合って支援の仕方を工夫し、子供に信頼してもらえる存在になるよう努力していました。その結果、同校の生徒は落ち着て、かつ生き生きと学習に取り組んでいました。「自主性=放任」という思い込みの教育観の転換が必要だと強く反省した次第です。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「政策立案に統計学的思考が不可欠
少子高齢化や地方の過疎化が進む中、政府や自治体では効率的な行政運営が不可欠であり、政策立案者には、課題を明確にして必要なデータを集め、分析するという統計学で学ぶ数学的思考力が求められています。しかし、現在の大学入試制度では文系志望者に数学を必須としない場合が多く、結果として学生に数学的思考力が十分に育めていません。早い段階から文系と理系に分ける高校教育を見直し、文系学生にも微分積分や確率論を学び数学的思考力を求めるような入試制度の改革が必要です。
2.3面 天録時評 「空飛ぶ救命艇
山口県岩国市に配備される海上自衛隊の救難飛行艇US-2は、世界唯一の外洋救難飛行艇部隊として一千人以上の人命を救助してきました。高コストゆえに継続も危ぶまれましたが、国際的にも代替のない技術資産であり、国際的な「救難インフラ」と位置付ければ外交資源としての活路も開けてきます。また、岩国市にはかねてから「飛行艇ミュージアム(仮称)」の整備構想がありますが、国際情勢が厳しい中、「基地と共存する街」の枠を超えて、「国の安全を学び、未来を切り拓く聖地」として政府挙げて整備していくことが重要です。
4.5面 レポート「岐阜市の『誰一人取り残さない教育』
わが国では全国的に不登校児童生徒が過去最多になっています。こうした中、岐阜市では「誰一人取り残さない教育」の実現を目指した学校運営の推進で、不登校児童生徒の増加の抑制に成功しています。そこで、岐阜市が取り組んだ、子供の心の変化を可視化して児童生徒の心のケアに活かす教育アプリ「ここタン」の導入や、「草潤メソッド」と呼ばれる不登校を経験した生徒が通う草潤中学校での取り組みを基にした「校内フリースペース」の設置について、岐阜市教育委員会教育長の水川和彦氏に聞きました。
7面 天録時評 「中国の文化的制裁に冷静な対応を
高市首相の「台湾有事」を巡る「存立危機事態になりうるケース」という発言を受け、中国はわが国に対し経済的、文化的圧力を行っています。こうした中国の外交的圧力に屈せず、冷静に状況を見極め、長期的な視点で日中関係を捉えることが重要です。
3面 巷 露 「働けることの有難さ」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「政策立案に統計学的思考が不可欠
文・理関係なく大学入試で数学を必須に」
少子高齢化や地方の過疎化が進む中、政府や自治体では効率的な行政運営が不可欠であり、政策立案者には、課題を明確にして必要なデータを集め、分析するという統計学で学ぶ数学的思考力が求められています。しかし、現在の大学入試制度では文系志望者に数学を必須としない場合が多く、結果として学生に数学的思考力が十分に育めていません。早い段階から文系と理系に分ける高校教育を見直し、文系学生にも微分積分や確率論を学び数学的思考力を求めるような入試制度の改革が必要です。
2.3面 天録時評 「空飛ぶ救命艇
『US―2』と安全保障都市・岩国
基地との共存を超えて、安全保障を学ぶ聖地に」
山口県岩国市に配備される海上自衛隊の救難飛行艇US-2は、世界唯一の外洋救難飛行艇部隊として一千人以上の人命を救助してきました。高コストゆえに継続も危ぶまれましたが、国際的にも代替のない技術資産であり、国際的な「救難インフラ」と位置付ければ外交資源としての活路も開けてきます。また、岩国市にはかねてから「飛行艇ミュージアム(仮称)」の整備構想がありますが、国際情勢が厳しい中、「基地と共存する街」の枠を超えて、「国の安全を学び、未来を切り拓く聖地」として政府挙げて整備していくことが重要です。
4.5面 レポート「岐阜市の『誰一人取り残さない教育』
子供の小さなSOSを可視化し拾う『ここタン』
『草潤メソッド』で行きたくなる学校づくり」に」
わが国では全国的に不登校児童生徒が過去最多になっています。こうした中、岐阜市では「誰一人取り残さない教育」の実現を目指した学校運営の推進で、不登校児童生徒の増加の抑制に成功しています。そこで、岐阜市が取り組んだ、子供の心の変化を可視化して児童生徒の心のケアに活かす教育アプリ「ここタン」の導入や、「草潤メソッド」と呼ばれる不登校を経験した生徒が通う草潤中学校での取り組みを基にした「校内フリースペース」の設置について、岐阜市教育委員会教育長の水川和彦氏に聞きました。
7面 天録時評 「中国の文化的制裁に冷静な対応を
政府は毅然とした対応を豪州から学べ」
高市首相の「台湾有事」を巡る「存立危機事態になりうるケース」という発言を受け、中国はわが国に対し経済的、文化的圧力を行っています。こうした中国の外交的圧力に屈せず、冷静に状況を見極め、長期的な視点で日中関係を捉えることが重要です。
3面 巷 露 「働けることの有難さ」
6面 小児科医の視点⑩
「家庭でのスマホ利用」
7面 役立つ最新用語96
「いじめの重大化を防ぐ
『留意事項集』を文科省が公表」
8面 日本の肖像142 白洲次郎(下)
「戦中戦後、いかなる国難に出遭っても
揺るぎなき原則を貫き通した男」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2077号 編集便りNo.488 2025/12/05
中国駐日大使は、高市首相の台湾有事における『存立危機事態』発言を巡り、Xに「台湾省の各界は高市早苗氏に対し、その誤った言論について謝罪するよう求めている」と投稿しました。中国共産党は「台湾省」と国内扱いで謝罪を求めるなど、情報戦により日本国内の混乱や誤解へ誘導する動きを続けています。高市首相が国会で示した台湾有事への見解は、あくまで日本の存立危機を想定した正当な発言であり、中国の圧力に屈して謝罪すれば抑止力は低下します。われわれ国民も、平和を守るためにこうした情報戦に騙されない姿勢を持つことが重要です。それでは紙面案内です。(田村)
1.2面 天録時評「高市発言は抑止力向上のために不可避
高市早苗総理が国会答弁で、台湾有事は『存立危機事態』に成り得ると明言しました。この発言への一部野党や新聞の批判を見て、中国政府も徐々に批判姿勢を強め、渡航自粛や水産物の輸入停止などを打ち出してきました。しかし、中国は急速な軍拡に取り組み、わが国周辺での軍事活動も強化し、台湾はもとより西太平洋を中国の支配下に置こうとしています。台湾に対する中国の武力行使を思いとどまらせる抑止力向上のためには、わが国は武力行使に反対する姿勢を明示し、国際秩序やわが国の安全を守るために米国をはじめとする友好国との協力関係を促進する方針を世界に表明することが不可欠です。同時に、わが国の安全保障の実情を国民に理解してもらうことも大事です。
3面 天録時評「環境に影響のない除去土壌は『処理土』と統一を
福島第一原子力発電所の事故後の除染活動で集められた『除去土壌』で、減容処理などにより環境に影響を与えない放射線水準となったものは『処理土』として、公共事業などに再生利用しなければなりません。事故から14年を経て、半減期による減衰などもあって、既に7割近くは放射線被曝の危険性は一般土壌と大差ありません。『処理水』の海洋放出では、反対運動を煽るような新聞やテレビの偏向報道により、時間も経費も大浪費しました。今回は同じ過ちを繰り返さないよう、政府挙げての対策が急務であるとともに、国民も正確な情報に基づいて行動しなければなりません。
4.5面 レポート「国際歴史論戦研究所主催 対国連活動報告会
「慰安婦=性奴隷」との嘘を浸透させるなど、左派・共産主義勢力の牙城となっている「国連」で、平成26年(2014)から11年間、わが国の保守系団体として継続して対抗する活動を展開してきた経験とノウハウを伝えようと、一般社団法人国際歴史論戦研究所主催の「対国連活動報告会」が11月15日に都内で開催されました。日本の名誉を守ろうとする地道で大切な民間活動を紹介します。
2面 巷 露 「大東亜戦争の教訓を学ぶ」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1.2面 天録時評「高市発言は抑止力向上のために不可避
台湾有事を防止するため明確な基本方針の伝達を
中国共産党の威嚇的揺さぶりに右往左往するな」
高市早苗総理が国会答弁で、台湾有事は『存立危機事態』に成り得ると明言しました。この発言への一部野党や新聞の批判を見て、中国政府も徐々に批判姿勢を強め、渡航自粛や水産物の輸入停止などを打ち出してきました。しかし、中国は急速な軍拡に取り組み、わが国周辺での軍事活動も強化し、台湾はもとより西太平洋を中国の支配下に置こうとしています。台湾に対する中国の武力行使を思いとどまらせる抑止力向上のためには、わが国は武力行使に反対する姿勢を明示し、国際秩序やわが国の安全を守るために米国をはじめとする友好国との協力関係を促進する方針を世界に表明することが不可欠です。同時に、わが国の安全保障の実情を国民に理解してもらうことも大事です。
3面 天録時評「環境に影響のない除去土壌は『処理土』と統一を
公共工事への再生利用で福島県の復興を促進!!」
福島第一原子力発電所の事故後の除染活動で集められた『除去土壌』で、減容処理などにより環境に影響を与えない放射線水準となったものは『処理土』として、公共事業などに再生利用しなければなりません。事故から14年を経て、半減期による減衰などもあって、既に7割近くは放射線被曝の危険性は一般土壌と大差ありません。『処理水』の海洋放出では、反対運動を煽るような新聞やテレビの偏向報道により、時間も経費も大浪費しました。今回は同じ過ちを繰り返さないよう、政府挙げての対策が急務であるとともに、国民も正確な情報に基づいて行動しなければなりません。
4.5面 レポート「国際歴史論戦研究所主催 対国連活動報告会
歴史論戦』と現在進行形の課題:
藤木俊一上席研究員が講演
3者対談:11年間の対国連活動の奮闘
日本を守るために」
「慰安婦=性奴隷」との嘘を浸透させるなど、左派・共産主義勢力の牙城となっている「国連」で、平成26年(2014)から11年間、わが国の保守系団体として継続して対抗する活動を展開してきた経験とノウハウを伝えようと、一般社団法人国際歴史論戦研究所主催の「対国連活動報告会」が11月15日に都内で開催されました。日本の名誉を守ろうとする地道で大切な民間活動を紹介します。
2面 巷 露 「大東亜戦争の教訓を学ぶ」
6面 地域便り 岐阜県
「終戦80年―感謝のこころをつなぐ
岐阜県プロジェクトの取り組み②
~郷土の先人黒木博司少佐に学ぶ『楠公精神』~
7面 レポート 「子供の自主性を尊重した授業づくり
課題に応じて仲間を作り対話で共に学び合う」
岐阜市立藍川東中学校
8面 日本の肖像141 白洲次郎(中)
「出生時から洋風仕立ての坊ちゃんが
イギリス留学で〝日本魂〟に目覚める」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2076号 編集便りNo.487 2025/11/21
文科省が「児童生徒の問題行動・不登校等に関する調査(2024年度)」を公表しました。全国の小学校で起きた子供の暴力件数は8万2997件と急増し、暴力の低年齢化が進んでいるとのことです。様々な原因が挙げられますが、親自身が怒りに任せて子供を叱る、あるいは店員などの弱い立場の人に対して横柄で攻撃的な態度で接するなど、身近な大人の姿の反映のようにも思います。親はもちろん、大人世代の一人一人が、弱い立場の人に優しく、強い立場の人にも理不尽な行為には是正を求めるなど、子供世代の範となるような言動を心掛けたいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「原子力政策
原子力発電所の再稼働は、国民生活の負担軽減と日本経済の持続的成長に直結する最優先の政策です。特に、電気料金の高騰が家計と企業活動を圧迫している中で、安価で安定的な電力供給ができる原子力の活用は、最も即効的で持続可能な対策と言えます。ところが、それを阻んでいるのが、特定重大事故等対処施設(特重施設)の設置を「設計・工事計画認可から5年以内」に完了しなければならないという硬直的な規定です。政治の責任で、特重施設の設置を再稼働の条件から分離すべきです。
2面 天録時評 「規制緩和なくして経済成長なし
実質賃金が下がり続け、国民全体が貧困化する経済の沈滞を招いた原因の一つに、新規参入や新たな技術の導入などを阻害した様々な規制があります。この規制緩和なくして、高市政権の成長戦略の成功はあり得ません。秩序や伝統を尊重しつつ、変革に挑戦する勇気が今求められています。
3面 天録時評 「老朽化する分譲マンション対策が急務
マンションブームの時機に建設された分譲マンションが、築40年、50年を超えて、大規模修繕や建て替えが必要な時期を迎えてきます。しかし、多くは積立金が不足している上に、空室が増えれば修繕も建て替えも至難になります。空室だらけの老朽マンションの増加を避けなければなりません。政府は、早期の建て替えを奨励する補助事業の拡大などで、建て替えの奨励に取り組むべきです。
4.5面インタビュー「攻めの文化政策と国立劇場の
文化は国家の精神的な支柱となります。過去から現在、未来へとつなぐ文化の伝承は国民の紐帯(ちゅうたい)ともなり、社会の絆を育み、未来への希望ともなります。さらに、文化は産業を興し、地域経済の活性化にも貢献します。経済的に困難な時代だからこそ、文化政策を怠ってはなりません。そこで、自民党文化立国調査会会長を長らく務めてこられた山谷えり子参議院議員に文化政策と、最近話題の国立劇場の再整備について聞きました。
2面 巷 露 「生き甲斐ある人生を」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「原子力政策
特重施設を再稼働の条件から分離を
エネルギー安全保障と
国民生活安定に逆行する現制度」
原子力発電所の再稼働は、国民生活の負担軽減と日本経済の持続的成長に直結する最優先の政策です。特に、電気料金の高騰が家計と企業活動を圧迫している中で、安価で安定的な電力供給ができる原子力の活用は、最も即効的で持続可能な対策と言えます。ところが、それを阻んでいるのが、特定重大事故等対処施設(特重施設)の設置を「設計・工事計画認可から5年以内」に完了しなければならないという硬直的な規定です。政治の責任で、特重施設の設置を再稼働の条件から分離すべきです。
2面 天録時評 「規制緩和なくして経済成長なし
秩序を尊重しつつ変革に挑戦を」
実質賃金が下がり続け、国民全体が貧困化する経済の沈滞を招いた原因の一つに、新規参入や新たな技術の導入などを阻害した様々な規制があります。この規制緩和なくして、高市政権の成長戦略の成功はあり得ません。秩序や伝統を尊重しつつ、変革に挑戦する勇気が今求められています。
3面 天録時評 「老朽化する分譲マンション対策が急務
解体困難な共同住宅の空室問題が深刻化」
マンションブームの時機に建設された分譲マンションが、築40年、50年を超えて、大規模修繕や建て替えが必要な時期を迎えてきます。しかし、多くは積立金が不足している上に、空室が増えれば修繕も建て替えも至難になります。空室だらけの老朽マンションの増加を避けなければなりません。政府は、早期の建て替えを奨励する補助事業の拡大などで、建て替えの奨励に取り組むべきです。
4.5面インタビュー「攻めの文化政策と国立劇場の
再整備の重要性を語る」
参議院議員 山谷えり子氏
文化は国家の精神的な支柱となります。過去から現在、未来へとつなぐ文化の伝承は国民の紐帯(ちゅうたい)ともなり、社会の絆を育み、未来への希望ともなります。さらに、文化は産業を興し、地域経済の活性化にも貢献します。経済的に困難な時代だからこそ、文化政策を怠ってはなりません。そこで、自民党文化立国調査会会長を長らく務めてこられた山谷えり子参議院議員に文化政策と、最近話題の国立劇場の再整備について聞きました。
2面 巷 露 「生き甲斐ある人生を」
6面 小児科医の視点⑨
「インフルエンザ対策」当堂游
7面 天録時評 「多文化共生で日本の文化が破壊
給食の宗教的配慮は家庭がすること」
役立つ最新用語95
「犯罪被害者の立ち直りを支援する
『『被害者担当保護司』」
8面 日本の肖像140 白洲次郎(上)
「『従順ならざる唯一の日本人』と
GHQが評した希代の日本男児」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2075号 編集便りNo.486 2025/11/07
今年は全国各地で、人がクマに襲われるという被害が多数報告されています。専門家によると、クマが襲って殺した人を食べることで肉の味を覚え、人を食べる習慣を持つクマが増えているとの指摘があります。人間とクマが偶発的に遭遇したとき、クマが驚いて襲ってくるのではなく、人間をエサとして狙ってくる危険性が高まっていると言えます。現在、クマの駆除は自治体が狩猟免許を持つハンターに依頼することになっていますが、その数は少なく十分に対応できていません。警察でも対応できるようにすることが急務であると同時に、被害増大の原因究明も急がれます。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「歴史の節目に自公連立を解消
自民党と公明党による連立政権が26年ぶりに解消されました。これは単なる政党間の協力関係の終焉にとどまりません。「選挙対策」から、独立と主権を守り日本再生を図る「政策本位」の連立としなければなりません。国民もバラマキ政策を排し、規制緩和などによる新たな産業創生や地方再生のための投資が不可欠であることを認識し、協力することが大切です。
2面 天録時評 「自助と共助で地域の持続的発展を
人口減少、財政難などで生活の質の向上や地域活性化は容易ではありません。しかし、地域には様々な物や文化、そして人材が存在します。工夫し、有効活用することによって持続的な地域の発展も可能です。悲観的に考えるのではなく、積極的に肯定的な価値を見出す発想が求められます。
3面 天録時評 「レアアースのリサイクル産業育成が急務
中国のレアアース輸出規制強化により、ハイテク産業のみならず防衛産業も深刻な影響を受けています。安全保障に直結するだけに、米国は大きな怒りを表明しましたが、わが国も従来から取り組んでいた対抗策を各国と協力して迅速に強化しなければなりません。とりわけ、持続可能な社会づくりの観点から、国を挙げてのレアアースのリサイクル産業育成が急務です。。
4.5面インタビュー「自民党結党70年
自民党は今月15日で立党70周年を迎えます。高市早苗新総裁は、「政治は国民のもの」という自民党立党宣言の精神に立ち返り、国民の信頼を取り戻すことを目指す姿勢を示しています。そこで、政党史に詳しい福冨健一氏(現・自民党本部憲法改正実現本部事務局顧問)に、自民党の立党の精神、経緯等について分かり易く語ってもらいました。
2面 巷 露 「深海への挑戦を」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「歴史の節目に自公連立を解消
『選挙対策』から『政策本位』の連立を求める」
自民党と公明党による連立政権が26年ぶりに解消されました。これは単なる政党間の協力関係の終焉にとどまりません。「選挙対策」から、独立と主権を守り日本再生を図る「政策本位」の連立としなければなりません。国民もバラマキ政策を排し、規制緩和などによる新たな産業創生や地方再生のための投資が不可欠であることを認識し、協力することが大切です。
2面 天録時評 「自助と共助で地域の持続的発展を
ない物探しを止め、有る物の価値を探し出す」
人口減少、財政難などで生活の質の向上や地域活性化は容易ではありません。しかし、地域には様々な物や文化、そして人材が存在します。工夫し、有効活用することによって持続的な地域の発展も可能です。悲観的に考えるのではなく、積極的に肯定的な価値を見出す発想が求められます。
3面 天録時評 「レアアースのリサイクル産業育成が急務
再利用の義務付けで持続可能な社会実現へ」
中国のレアアース輸出規制強化により、ハイテク産業のみならず防衛産業も深刻な影響を受けています。安全保障に直結するだけに、米国は大きな怒りを表明しましたが、わが国も従来から取り組んでいた対抗策を各国と協力して迅速に強化しなければなりません。とりわけ、持続可能な社会づくりの観点から、国を挙げてのレアアースのリサイクル産業育成が急務です。。
4.5面インタビュー「自民党結党70年
保守主義の原点と未来への責任を語る
『政治は国民のもの』の精神に立ち戻るとは」
自由民主党憲法改正実現本部事務局顧問
福冨健一氏
自民党は今月15日で立党70周年を迎えます。高市早苗新総裁は、「政治は国民のもの」という自民党立党宣言の精神に立ち返り、国民の信頼を取り戻すことを目指す姿勢を示しています。そこで、政党史に詳しい福冨健一氏(現・自民党本部憲法改正実現本部事務局顧問)に、自民党の立党の精神、経緯等について分かり易く語ってもらいました。
2面 巷 露 「深海への挑戦を」
6面 天録時評 「在日外国人 問題行動に毅然と対応を
『郷に入れば郷に従え』の徹底が不可欠
7面 天録時評 「大学の受験資格制度の導入を
選抜制入試の主流化で教育の質が低下」
役立つ最新用語94
「子供の健全育成を支える
『法廷養育費制度』
8面 日本の肖像139 井上円了(下)
「妖怪学を通じて日本固有の文化と技芸を愛し、
一国独立の精神に至る哲学の道を開拓する」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2074号 編集便りNo.485 2025/10/17
自民党の総裁に高市早苗衆議院議員が選ばれました。初の女性総裁であり、臨時国会で内閣総理大臣に選ばれれば、初の女性総理誕生です。大変に困難な時代に誕生する初の女性総理であり、問われるのは性別ではなくその手腕です。物価高対策や賃上げのために積極財政を行えば円安となり、さらなる物価高騰を招きかねないなど国政の舵取りは至難です。国民の安心、安全な生活や平和を守るためには、国会議員はもとより国民も目先の利益よりも、国益や社会全体の利益を優先することが必要でしょう。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「重要性を増す原子力政策
10月26日は「原子力の日」です。昭和38年、日本で初めて原子力発電の実験に成功した日です。その後、原子力発電はわが国の経済成長を支えてきましたが、平成23年の東京電力・福島第一原子力発電所事故で厳しい冬の時代に入っていきました。そして今、不安定な国際情勢や地球環境への関心の高まりの中、電力の安定供給と脱炭素の両方を達成する必須の電源として、政府は「最大限の活用」へと大きく舵を切りました。「原子力の日」にちなんで、改めて原子力発電の新増設への具体的な取り組みを強く求めます。
2面 天録時評 「人気投票的な選挙報道の禁止を
選挙の公平性を保つことは容易ではありません。公職選挙法では有権者の判断に影響を与える人気投票の公表を禁止していますが、新聞やテレビでは人気投票と同じような影響を与える報道が行われています。とりわけ、候補者の支持率の順位が分かる選挙の情勢報道は、有権者に大きな影響を与え、投票率の低下を招いており、禁止すべきです。
3面 天録時評 「スマホの長時間利用の防止に法規制を
愛知県豊明市が10月1日から施行したスマホ規制条例に反対する声が少なくありません。しかし、スマホの長時間利用はもちろん、13歳未満で与えられた場合に心身に深刻な影響を与えることは明らかと言われています。個人の自由の保障も大切ですが、未成年者の心身に深刻な害を与える以上、飲酒や喫煙を規制するのと同様に、子供たちを守るための法規制は必要です。
4.5面 天録時評「原子力の日」特集
わが国が将来にわたって豊かな国として存続し、すべての国民が希望をもって暮らせる社会を実現するためには、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していく必要があります。こうした考えの基に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力の位置付けを「可能な限り依存度を低減」から「最大限活用」へと方向転換しました。しかし、原子力政策は停滞し、新増設の具体化は宙に浮いたままです。このままだと国民の生活はますます困窮化します。「原子力の日」を前に、国民として考えるべき原子力政策の課題をまとめました。
2面 巷 露 「感謝を捧げる神嘗祭」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「重要性を増す原子力政策
政治家の実行と国民の責任が問われる」
10月26日は「原子力の日」です。昭和38年、日本で初めて原子力発電の実験に成功した日です。その後、原子力発電はわが国の経済成長を支えてきましたが、平成23年の東京電力・福島第一原子力発電所事故で厳しい冬の時代に入っていきました。そして今、不安定な国際情勢や地球環境への関心の高まりの中、電力の安定供給と脱炭素の両方を達成する必須の電源として、政府は「最大限の活用」へと大きく舵を切りました。「原子力の日」にちなんで、改めて原子力発電の新増設への具体的な取り組みを強く求めます。
2面 天録時評 「人気投票的な選挙報道の禁止を
公平性を損ない投票率低下も招く」
選挙の公平性を保つことは容易ではありません。公職選挙法では有権者の判断に影響を与える人気投票の公表を禁止していますが、新聞やテレビでは人気投票と同じような影響を与える報道が行われています。とりわけ、候補者の支持率の順位が分かる選挙の情勢報道は、有権者に大きな影響を与え、投票率の低下を招いており、禁止すべきです。
3面 天録時評 「スマホの長時間利用の防止に法規制を
未成年者の心身への弊害は大きい」
愛知県豊明市が10月1日から施行したスマホ規制条例に反対する声が少なくありません。しかし、スマホの長時間利用はもちろん、13歳未満で与えられた場合に心身に深刻な影響を与えることは明らかと言われています。個人の自由の保障も大切ですが、未成年者の心身に深刻な害を与える以上、飲酒や喫煙を規制するのと同様に、子供たちを守るための法規制は必要です。
4.5面 天録時評「原子力の日」特集
「原子力への理解の促進を」
わが国が将来にわたって豊かな国として存続し、すべての国民が希望をもって暮らせる社会を実現するためには、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素を同時に実現していく必要があります。こうした考えの基に策定された第7次エネルギー基本計画では、原子力の位置付けを「可能な限り依存度を低減」から「最大限活用」へと方向転換しました。しかし、原子力政策は停滞し、新増設の具体化は宙に浮いたままです。このままだと国民の生活はますます困窮化します。「原子力の日」を前に、国民として考えるべき原子力政策の課題をまとめました。
2面 巷 露 「感謝を捧げる神嘗祭」
6面 地域だより 岐阜県
「戦後80年-感謝のこころをつなぐ
岐阜県プロジェクトの取り組み①
~届け!日本を守った若者たちの想い~」
7面 小児科医の視点⑧
「起立性調節障害と起立不耐症」
8面 日本の肖像138 井上円了(中)
「幽霊や妖怪を否定せず、自ら疑い、問い、
考える力を養う『妖怪学』を唱える」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2073号 編集便りNo.484 2025/10/03
静岡県伊東市の田久保市長の学歴詐称問題をはじめ、群馬県前橋市の小川市長の既婚男性とのホテル問題など、自治体の首長の不祥事が報道されています。こうした問題は、政治不信を増幅させ、市民の政治離れを加速させてしまいます。首長には一般市民以上の高い倫理観が求められるのは当然ですが、首長選挙でも地元テレビ局で候補者の政策討論会等を開催・放送し、市民がその情報を基に投票するといった選挙のあり方を改善する時期にきているのではないでしょうか。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「自民党は結党の原点に立ち返れ!
自民党は先の参院選の総括文書で「解党的出直し」に取り組み「真の国民政党に生まれ変わる」と宣言しました。その後、石破首相は辞任しましたが、新しい総裁がこれに取り組まなければ、自民党の再生は期待できません。一方、国民もより良い政治、その先の明るい未来を求めるならば、主権者としての自覚を持ち、政治に積極的に関わっていくことが必要です。
2面 天録時評 「国策としての洋上風力発電事業の中止を
三菱商事が洋上風力発電事業から撤退しました。欧米でも採算割れや見通しが立たず、撤退が続いています。これは、単なる三菱商事の「事業失敗」ではなく、洋上風力を国策として推進する「政策の失敗」です。わが国には風力発電の適地は少なく、一方で台風や落雷が多く、送電網などを含めた総合的な発電コストは洋上風力が最も高くなります。電力料金の高騰を招く洋上風力発電事業を国策として推進するようなことは直ちに中止すべきです。
3面 天録時評 「『国民共有の財産』との意識改革を
漁業も農業同様、占領行政の後遺症から抜け出せず衰退が続いています。世界各国は「海洋・水産資源は国民共有の財産」として科学的な資源管理を政府の責任として取り組み、漁業を成長させています。わが国の漁業振興には、稚魚などの乱獲防止などの水産行政の抜本改革が急がれます。漁協や漁業者は「早い者勝ち」という考え方を捨て、水産資源は国民共有の財産との意識を強く持ち、資源保護に取り組むべきです。
6面 天録時評 「義務教育の性教育
“人間と性”教育研究協議会(性教協)が、「性交を教えてはいけない」と解釈される学習指導要領の「はどめ規定」の撤廃を求めています。性教協は過去に過激な性教育を行ってきた経緯があり、「人権尊重」や「自己決定権」、「共生」の名のもと、「性交」偏重の性教育を学校現場に浸透させようとするものだと指摘せざるを得ません。一方で、義務教育の性教育は不十分です。性道徳の涵養とともに、児童生徒の発達段階に応じて、生物学的な妊娠の仕組みや性的欲望などの自己の体と心の科学的な知識を与えることが必要です。
2面 巷 露 「東ドイツの消滅」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「自民党は結党の原点に立ち返れ!
国民も主権者としての自覚を持ち、
政治に積極的に関与を」
自民党は先の参院選の総括文書で「解党的出直し」に取り組み「真の国民政党に生まれ変わる」と宣言しました。その後、石破首相は辞任しましたが、新しい総裁がこれに取り組まなければ、自民党の再生は期待できません。一方、国民もより良い政治、その先の明るい未来を求めるならば、主権者としての自覚を持ち、政治に積極的に関わっていくことが必要です。
2面 天録時評 「国策としての洋上風力発電事業の中止を
国民負担の増大と産業競争力の低下を招く」
三菱商事が洋上風力発電事業から撤退しました。欧米でも採算割れや見通しが立たず、撤退が続いています。これは、単なる三菱商事の「事業失敗」ではなく、洋上風力を国策として推進する「政策の失敗」です。わが国には風力発電の適地は少なく、一方で台風や落雷が多く、送電網などを含めた総合的な発電コストは洋上風力が最も高くなります。電力料金の高騰を招く洋上風力発電事業を国策として推進するようなことは直ちに中止すべきです。
3面 天録時評 「『国民共有の財産』との意識改革を
水産資源 保護なくして漁業振興は不可能」
漁業も農業同様、占領行政の後遺症から抜け出せず衰退が続いています。世界各国は「海洋・水産資源は国民共有の財産」として科学的な資源管理を政府の責任として取り組み、漁業を成長させています。わが国の漁業振興には、稚魚などの乱獲防止などの水産行政の抜本改革が急がれます。漁協や漁業者は「早い者勝ち」という考え方を捨て、水産資源は国民共有の財産との意識を強く持ち、資源保護に取り組むべきです。
6面 天録時評 「義務教育の性教育
正しい性知識と性道徳の涵養を計画的に
発達段階を無視した過激な性教育に要注意」
“人間と性”教育研究協議会(性教協)が、「性交を教えてはいけない」と解釈される学習指導要領の「はどめ規定」の撤廃を求めています。性教協は過去に過激な性教育を行ってきた経緯があり、「人権尊重」や「自己決定権」、「共生」の名のもと、「性交」偏重の性教育を学校現場に浸透させようとするものだと指摘せざるを得ません。一方で、義務教育の性教育は不十分です。性道徳の涵養とともに、児童生徒の発達段階に応じて、生物学的な妊娠の仕組みや性的欲望などの自己の体と心の科学的な知識を与えることが必要です。
2面 巷 露 「東ドイツの消滅」
4・5レポート 「悠仁親王殿下の成年式・
加冠の儀をお祝いする集い
皇位継承の法整備の必要性も確認」
7面 天禄時評 「男女の違いを認める道徳教育こそ
一面的な指標に基づく記述は不適切」
役立つ最新用語93
「価格が安定している暗号資産
『ステーブルコイン』がこの秋に」
8面 日本の肖像137 井上円了(上)
「心の世界の近代化を図るため、
『妖怪』『幽霊』の調査研究に取り組む」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2072号 編集便りNo.483 2025/09/19
神奈川県鎌倉市など、日本のアニメや漫画の舞台となった場所を観光する「聖地巡礼」が人気となっていますが、外国人観光客による住民の私有地内まで侵入しての写真撮影、公道上でのごみのポイ捨てや糞尿の排泄といった迷惑行為が後を絶ちません。対策として、ホテルなどの宿泊施設や航空会社を通じて徴収する入国税を導入するという方法があります。現在、フランスやベルギー、スペインのバルセロナなど世界の25以上の国や地域で導入されています。わが国も外国人対象の入国税を導入して、観光公害対策を強化し、住民生活を守ってほしいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「中国の『抗日戦勝』は真っ赤なウソ
中国共産党は日本軍とはまともに戦っていませんので、中国共産党政府が「抗日戦勝」の言葉を口にすること自体が虚構の物語です。しかし、現実は国際舞台で堂々と語り、ロシアや北朝鮮などそれを是とする国々が集まって盛大な行事を開きました。わが国への間違った歴史認識を放置することによる国益の損失は計り知れません。国家の名誉と信用を棄損する誤った宣伝工作に対処するため、内外に正しい事実を広報する部署を内閣府に設置すべきです。
2面 天録時評 「皆保険制度維持に国民の協力が不可欠
救命医療や最新の治療法を導入している公的な病院が経営に苦しんでいます。皆保険制度を維持し、最新医療を誰もが受けられるようにするためには、医療制度改革だけでなく、資産のある高齢者の医療機関への寄付なども不可欠です。
3面 天録時評 「変容するドル基軸通貨体制㊦
ドルの基軸通貨体制はしばらく続きますが、米国政治への信頼低下は各国のドル離れを促進します。ドルは暴落がなくとも価値は低下し、ドルに偏っている資産をもつわが国は大きな打撃を受ける可能性があります。経済も安全保障も全面的に米国に依存した戦後体制からの脱却を目指し、ドルへの依存度を低下させ、主権国家として自立した国家戦略の構築が急がれます。
7面 天録時評 「未だに残る『階級闘争史観』に基づく歴史記述
中学校の歴史教科書では、出版社によっては依然として階級闘争史観に基づく記述が残っています。今回は、室町時代の土一揆の記述について『学び舎』『東京書籍』『育鵬社』『自由社』の四社を比較し、子供たちに「わが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる」観点からは『自由社』の教科書が一番ふさわしいことを紹介します。
2面 巷 露 「プラザ合意が分岐点」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「中国の『抗日戦勝』は真っ赤なウソ
政府は正しい情報発信のための部署設置を」
中国共産党は日本軍とはまともに戦っていませんので、中国共産党政府が「抗日戦勝」の言葉を口にすること自体が虚構の物語です。しかし、現実は国際舞台で堂々と語り、ロシアや北朝鮮などそれを是とする国々が集まって盛大な行事を開きました。わが国への間違った歴史認識を放置することによる国益の損失は計り知れません。国家の名誉と信用を棄損する誤った宣伝工作に対処するため、内外に正しい事実を広報する部署を内閣府に設置すべきです。
2面 天録時評 「皆保険制度維持に国民の協力が不可欠
救命や最新の医療のために公的病院への寄付を」
救命医療や最新の治療法を導入している公的な病院が経営に苦しんでいます。皆保険制度を維持し、最新医療を誰もが受けられるようにするためには、医療制度改革だけでなく、資産のある高齢者の医療機関への寄付なども不可欠です。
3面 天録時評 「変容するドル基軸通貨体制㊦
米国への信頼低下で進むドル離れ
ドル全面依存から脱却する国家戦略を」
ドルの基軸通貨体制はしばらく続きますが、米国政治への信頼低下は各国のドル離れを促進します。ドルは暴落がなくとも価値は低下し、ドルに偏っている資産をもつわが国は大きな打撃を受ける可能性があります。経済も安全保障も全面的に米国に依存した戦後体制からの脱却を目指し、ドルへの依存度を低下させ、主権国家として自立した国家戦略の構築が急がれます。
7面 天録時評 「未だに残る『階級闘争史観』に基づく歴史記述
国民としての自覚を育む観点では
『自由社』の教科書が最適」
中学校の歴史教科書では、出版社によっては依然として階級闘争史観に基づく記述が残っています。今回は、室町時代の土一揆の記述について『学び舎』『東京書籍』『育鵬社』『自由社』の四社を比較し、子供たちに「わが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる」観点からは『自由社』の教科書が一番ふさわしいことを紹介します。
2面 巷 露 「プラザ合意が分岐点」
4・5レポート 「日本軍が大東亜戦争で『3千万人』
虐殺という歴史捏造本を論破
日米加の研究者19人が集結し
『『ジャパンズ・ホロコースト』の正体』発刊
出版記念シンポ
政府の対応を求める声明も発表」
6面 小児科医の視点⑥
「消化器外科医も不足」当堂游
役立つ最新用語92
「長時間使用で引き起こる『スマホ老眼』」
8面 日本の肖像136 岩崎弥太郎(補)
「独裁社長の岩崎弥太郎と
合本経営の渋沢栄一は水と油」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2071号 編集便りNo.482 2025/09/05
愛知県豊明市が、全住民を対象に仕事や勉強以外の自由時間にスマホを使う時間の目安を1日2時間以内とするよう促す条例案を市議会に提出しました。可決されれば10月1日に施行されるとのことです。スマホ依存の生活は、生活習慣が乱れ、不登校の要因になったり、健康を害する要因になったりしています。このような条例については賛否両論あります。法規制も必要ですが、親子でスマホの使い方のルールを決め、子供だけでなく親自身が守っていくことです。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「悠仁親王殿下の成年式を迎える今こそ
秋篠宮家長男の悠仁親王殿下が、9月6日の19歳の誕生日に成年式を迎えられます。秋篠宮文仁皇嗣殿下に続く皇位継承第二位の皇族として、将来、天皇にご即位されるご覚悟を一層持たれるであろうことは言うまでもありません。この機会にこそ、国会は懸案となっている日本古来の伝統に則った安定的な皇位継承に関する議論を加速させ、旧宮家の男系男子に皇族と養子縁組して復帰してもらうことを柱とする皇室典範の改正を急ぐべきです。
2面 天録時評 「食品添加物への不安解消に取り組め
週刊誌やSNSで食品添加物に関して、科学的に根拠のない虚偽情報が拡散され、食品添加物への不安を持つ国民が少なくありません。規制強化を求める政党もありますが、わが国の食品の安全性への取り組みは世界最高水準の科学的知見に基づいて行われています。政府、与党はもっと国民の信頼を高めるような広報活動を強化すべきです。
3面 天録時評 「変容するドル基軸通貨体制㊤
基軸通貨ドルの地位喪失を「世界大戦に負けるようなものだ」とトランプ大統領は述べました。強いドルと同時に製造業の競争力強化のためにドル安をも求めるという矛盾した政策を掲げたトランプ政権は、わが国などが保有する巨額の米国債を紙きれにしかねないような強硬策すら検討しています。米国への信認が薄らぎ、中露などの脱ドルの動きはさらに加速してきました。わが国もこの変化に対応する国家戦略の樹立を急ぐべきです。
6面 天録時評 「春・夏の甲子園の新聞社主催は不適切
今年も酷暑の中、夏の全国高校野球選手権大会が甲子園球場で行われました。予選から脱水症状で試合ができなくなる選手が多発するなど、この時期の屋外開催は大きな課題があります。にもかかわらず、主催者である朝日新聞社や高校野球連盟(高野連)は会場を変更するなどの抜本的改革ができません。その原因は、甲子園球場を「高校野球の聖地」に仕立て上げ、高校野球を営利に利用している新聞社、テレビにあります。高野連は、主催者から新聞社を外し、教育の一環として選手本位の大会とすべきです。
2面 巷 露 「ポツダム宣言を巡る一幕」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「悠仁親王殿下の成年式を迎える今こそ
国会は安定的な皇位継承のための法改正を」
秋篠宮家長男の悠仁親王殿下が、9月6日の19歳の誕生日に成年式を迎えられます。秋篠宮文仁皇嗣殿下に続く皇位継承第二位の皇族として、将来、天皇にご即位されるご覚悟を一層持たれるであろうことは言うまでもありません。この機会にこそ、国会は懸案となっている日本古来の伝統に則った安定的な皇位継承に関する議論を加速させ、旧宮家の男系男子に皇族と養子縁組して復帰してもらうことを柱とする皇室典範の改正を急ぐべきです。
2面 天録時評 「食品添加物への不安解消に取り組め
情報共有と対話により信頼と理解を」
週刊誌やSNSで食品添加物に関して、科学的に根拠のない虚偽情報が拡散され、食品添加物への不安を持つ国民が少なくありません。規制強化を求める政党もありますが、わが国の食品の安全性への取り組みは世界最高水準の科学的知見に基づいて行われています。政府、与党はもっと国民の信頼を高めるような広報活動を強化すべきです。
3面 天録時評 「変容するドル基軸通貨体制㊤
製造業空洞化は基軸通貨の宿命
トランプ政権の強引な政策が脱ドルを加速」
基軸通貨ドルの地位喪失を「世界大戦に負けるようなものだ」とトランプ大統領は述べました。強いドルと同時に製造業の競争力強化のためにドル安をも求めるという矛盾した政策を掲げたトランプ政権は、わが国などが保有する巨額の米国債を紙きれにしかねないような強硬策すら検討しています。米国への信認が薄らぎ、中露などの脱ドルの動きはさらに加速してきました。わが国もこの変化に対応する国家戦略の樹立を急ぐべきです。
6面 天録時評 「春・夏の甲子園の新聞社主催は不適切
新聞やテレビに営利目的で
利用される高校野球大会」
今年も酷暑の中、夏の全国高校野球選手権大会が甲子園球場で行われました。予選から脱水症状で試合ができなくなる選手が多発するなど、この時期の屋外開催は大きな課題があります。にもかかわらず、主催者である朝日新聞社や高校野球連盟(高野連)は会場を変更するなどの抜本的改革ができません。その原因は、甲子園球場を「高校野球の聖地」に仕立て上げ、高校野球を営利に利用している新聞社、テレビにあります。高野連は、主催者から新聞社を外し、教育の一環として選手本位の大会とすべきです。
2面 巷 露 「ポツダム宣言を巡る一幕」
4・5面講演録 「第36回いずみ会総会記念講演
『新世界秩序と日本の使命』」
元外務・防衛副大臣
衆議院前議員 中山泰秀氏
7面 天録時評 「NHK受信料
公用車のカーナビを標的
取れるところから受信料を
取る姿勢を改めよ」
役立つ最新用語91
「マダニに咬まれて起きるアレルギー
『アルファーガル症候群』」
8面 日本の肖像135 岩崎弥太郎(下)
「大事件となった『岩崎弥太郎=三菱』
対『渋沢栄一=共同運輸』」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2070号 編集便りNo.481 2025/08/15
今年の夏は、40度を超える気温を観測することも多く、例年以上に酷暑となっています。熱帯夜が続き、寝苦しく睡眠不足になりがちです。睡眠不足は熱中症などの心身の不調を招きます。そうならないためにも夜通し冷房を付けて快適な睡眠環境を整えることも必要です。私たちの暮らしを守り、経済を発展させるためには、電気の安定供給は欠かせません。スペインのように大規模停電を引き起こしたのでは、国民は安心して酷暑を乗り切ることはできません。安定供給確保のためにも、政府は既存の原子力発電所の再稼働はもちろん新設も推進すべきです。それでは紙面案内です。(田村)
1.2面 天録時評 「三度目の被爆を避ける安保戦略を
わが国は法的にも現実的にも独自の核武装はできないと思い込み、思考停止している国会議員が多数います。中、露、北朝鮮は核軍拡に邁進し、迎撃不可能な極超音速ミサイルが実戦配備され、核の脅威は高まるばかりです。わが国が核の脅威に対し、核抑止に正面から向き合うことが政府に突き付けられた安全保障上の重要課題です。被爆国だから核武装は許されないという自虐的な思考を払拭し、核抑止力を高めるための最善策を求める議論が急務です。
3面 天録時評 「参院選を振り返る
この度の参院選挙で、自民・公明の与党は大幅に議席を減らし、野党第一党の立憲民主党はほぼ現状維持、代わりに参政党や国民民主党が大きく躍進しました。この選挙結果でむしろはっきり言えることは、国民は保守的な政策を望んでいるということです。それに応えるためには、自民党が保守政党として自ら覚醒をすることこそ急がれます。
4面 講演録 「スペイン大停電の教訓 再エネ
4月28日正午過ぎにスペインとポルトガルで大規模停電が起きました。マドリードやバルセロナなど主要都市を含む広範囲で電力供給が途絶え、交通網や通信網が機能不全となり、復旧は翌日までかかりました。両国は、全電源に占める再生可能エネルギーの割合が高いのが特徴です。電圧制御の失敗が主たる原因とされ、改めて再エネの主力電源化の困難さを示しています。
7面 天録時評 「教員の働き方改革
わが国の学校では、教員の長時間労働などが問題になり、業務改善をはじめとする働き方改革が行われています。一方で、ICT(情報通信技術)教育やプログラミング教育など、新たな教育施策次から次へと導入されており、教員の負担減はなかなか実現しないのが現状です。せっかく導入した技術や施策が教員の負担を増大させたのでは、働き方改革に逆行してしまいます。地域の専門人材による支援体制を充実させることが必要です。
2面 巷 露 「『相互関税』の訳は不適切」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1.2面 天録時評 「三度目の被爆を避ける安保戦略を
核抑止力向上に最善の方途を求めよ」
わが国は法的にも現実的にも独自の核武装はできないと思い込み、思考停止している国会議員が多数います。中、露、北朝鮮は核軍拡に邁進し、迎撃不可能な極超音速ミサイルが実戦配備され、核の脅威は高まるばかりです。わが国が核の脅威に対し、核抑止に正面から向き合うことが政府に突き付けられた安全保障上の重要課題です。被爆国だから核武装は許されないという自虐的な思考を払拭し、核抑止力を高めるための最善策を求める議論が急務です。
3面 天録時評 「参院選を振り返る
国民は保守的な政策を望んでいる
自民党はリベラル思考の見直しを」
この度の参院選挙で、自民・公明の与党は大幅に議席を減らし、野党第一党の立憲民主党はほぼ現状維持、代わりに参政党や国民民主党が大きく躍進しました。この選挙結果でむしろはっきり言えることは、国民は保守的な政策を望んでいるということです。それに応えるためには、自民党が保守政党として自ら覚醒をすることこそ急がれます。
4面 講演録 「スペイン大停電の教訓 再エネ
主力電源化に新たな障壁」
4月28日正午過ぎにスペインとポルトガルで大規模停電が起きました。マドリードやバルセロナなど主要都市を含む広範囲で電力供給が途絶え、交通網や通信網が機能不全となり、復旧は翌日までかかりました。両国は、全電源に占める再生可能エネルギーの割合が高いのが特徴です。電圧制御の失敗が主たる原因とされ、改めて再エネの主力電源化の困難さを示しています。
7面 天録時評 「教員の働き方改革
地域専門人材の活用充実を
ICTやプログラミングの
教育導入で教員の負担が増加」
わが国の学校では、教員の長時間労働などが問題になり、業務改善をはじめとする働き方改革が行われています。一方で、ICT(情報通信技術)教育やプログラミング教育など、新たな教育施策次から次へと導入されており、教員の負担減はなかなか実現しないのが現状です。せっかく導入した技術や施策が教員の負担を増大させたのでは、働き方改革に逆行してしまいます。地域の専門人材による支援体制を充実させることが必要です。
2面 巷 露 「『相互関税』の訳は不適切」
5面 天禄時評 「柏崎刈羽原子力の再稼働を
新潟県知事の早期同意を望む」
コラム「震災時、住民の避難所と
なった女川原子力発電所」
6面 小児科医の視点⑤
「早寝早起き朝ごはん」当堂游
役立つ最新用語90
「運送業務の効率化につながる
『デジタルアドレス』」
8面 日本の肖像134 岩崎弥太郎(中)
「時代の波に乗り、明治政府と共に
ハンドルを握り、アクセルを踏み続ける」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2069号 編集便りNo.480 2025/08/01
先般の参議院選挙では、「日本人ファースト」をスローガンに外国人問題に取り組むと主張した参政党が躍進しました。SNS等を通じて有権者に分かりやすく政策を訴えたことが躍進の背景にあるようです。ただ、参政党などの新興政党は政策が十分に練られておらず、国防政策などで国益を損ねかねないような政策も公約として掲げています。選んだ国民は当選させて終わりではなく、政治行動をしっかりと監視する主権者としての責務を果たしたいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1.2面 天録時評 「戦歿者慰霊問題を考える(下)
「人は二度死ぬ」と言われます。一度は「肉体が滅んだ時」、二度目は「誰もがその人を忘れさった時」ですが、戦歿者を二度死なせてはなりません。ところが、約37万柱の戦歿者の遺骨が納骨されている千鳥ヶ淵戦没者墓苑に慰霊に訪れる国民は多くありません。海外戦歿者の遺骨収集事業への政府の姿勢も消極的でした。戦後80年を迎えて遺骨を収集し、遺族のもとへ送り届けることは困難さが増すばかりですが、国家の責任として遂行しなければなりません。海外に残された慰霊塔などの管理を含めて、政府と国会は戦歿者の慰霊問題に正面から向き合い、国家の責任を果たすべきです。
3面 天録時評 「参議院選挙
この度の参議院選挙でエネルギー政策に関する各党の論戦が低調だったことは極めて残念です。衆議院と違い、参議院には解散がないだけに、中長期の国家戦略を打ち出し、国民に是非を問うてこそ、参議院の存在価値もあります。そうした論戦を政治が避けているところが、国力の低下、政治不信の増大を招いているといっても過言ではないでしょう。エネルギー安全保障の確実な実行こそ政治の役割であり、責任です。
4.5面 講演録 「昭和史の真実と先人の心を語り継ぐ」
公益社団法人国民文化研究会主催による文化講演会が、ノンフィクション作家の早坂隆氏を講師に迎え、5月に都内で開かれました。演題は「戦後80年 昭和史の真実と先人の心を語り継ぐ」。真実を追求する丁寧な取材活動で定評のある早坂氏の「戦後日本を立て直したいなら歴史認識をまずしっかりしたものにすることがすべての基礎になる」との問題提起は傾聴に値します。講演要旨を紹介します。
6面 天録時評 「通知表廃止
教員の働き方改革の一環や、評定や所見が子供にとって分かりにくいなどの理由から、通知表を廃止する学校が散見されます。一方、通知表は子供の学習状況や学校での様子を知ることができる重要な資料の一つであり、廃止に不安を持つ保護者は多くいます。学校が通知表を廃止するのであれば、個人懇談で勉強の理解度、授業態度などを事細かく説明するなど、保護者の不安を払拭するための取り組みが不可欠です。
2面 巷 露 「再エネ 日常的補完が大変」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1.2面 天録時評 「戦歿者慰霊問題を考える(下)
外国要人も献花する戦歿者墓地の処遇を
37万柱が眠る千鳥ヶ淵戦没者墓苑」
「人は二度死ぬ」と言われます。一度は「肉体が滅んだ時」、二度目は「誰もがその人を忘れさった時」ですが、戦歿者を二度死なせてはなりません。ところが、約37万柱の戦歿者の遺骨が納骨されている千鳥ヶ淵戦没者墓苑に慰霊に訪れる国民は多くありません。海外戦歿者の遺骨収集事業への政府の姿勢も消極的でした。戦後80年を迎えて遺骨を収集し、遺族のもとへ送り届けることは困難さが増すばかりですが、国家の責任として遂行しなければなりません。海外に残された慰霊塔などの管理を含めて、政府と国会は戦歿者の慰霊問題に正面から向き合い、国家の責任を果たすべきです。
3面 天録時評 「参議院選挙
エネルギー政策の迷走で国力が低下
原子力の再稼働が進まないことこそ物価高の主因」
この度の参議院選挙でエネルギー政策に関する各党の論戦が低調だったことは極めて残念です。衆議院と違い、参議院には解散がないだけに、中長期の国家戦略を打ち出し、国民に是非を問うてこそ、参議院の存在価値もあります。そうした論戦を政治が避けているところが、国力の低下、政治不信の増大を招いているといっても過言ではないでしょう。エネルギー安全保障の確実な実行こそ政治の役割であり、責任です。
4.5面 講演録 「昭和史の真実と先人の心を語り継ぐ」
国民文化研究会の国民文化講座より
ノンフィクション作家の早坂隆氏が講演
公益社団法人国民文化研究会主催による文化講演会が、ノンフィクション作家の早坂隆氏を講師に迎え、5月に都内で開かれました。演題は「戦後80年 昭和史の真実と先人の心を語り継ぐ」。真実を追求する丁寧な取材活動で定評のある早坂氏の「戦後日本を立て直したいなら歴史認識をまずしっかりしたものにすることがすべての基礎になる」との問題提起は傾聴に値します。講演要旨を紹介します。
6面 天録時評 「通知表廃止
廃止の是非より保護者の不安解消が大事
懇談時の細かな情報提供で相互理解を」
教員の働き方改革の一環や、評定や所見が子供にとって分かりにくいなどの理由から、通知表を廃止する学校が散見されます。一方、通知表は子供の学習状況や学校での様子を知ることができる重要な資料の一つであり、廃止に不安を持つ保護者は多くいます。学校が通知表を廃止するのであれば、個人懇談で勉強の理解度、授業態度などを事細かく説明するなど、保護者の不安を払拭するための取り組みが不可欠です。
2面 巷 露 「再エネ 日常的補完が大変」
7面 レポート 「道徳授業 自ら考え議論し、
学びを日常生活に活かす
第20回岐阜県道徳教育奨励賞の
実践報告より」
8面 日本の肖像133 岩崎弥太郎(上)
「積極的かつ大胆な経営で
新興財閥を築き上げる」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2068号 編集便りNo.479 2025/07/18
近年、国政選挙等の候補者の街頭演説中に、候補者や支援者に対し罵声を浴びせたり暴行を加えたりして選挙活動を妨害する行為がニュースなどで目立ちます。政治に不満があるから、あるいは自分の思想信条と違うからなどの理由で、候補者が直接の脅威を感じるような行動は正当化されるものではありません。きちんと投票で意思表示を示すべきであり、警察には「選挙妨害行動」を徹底して取り締まってほしいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1.2面 天録時評「戦歿者慰霊問題を考える(上)
わが国は、昭和20年の大東亜戦争の終結から80年間、戦火に見舞われることなく、平和と繁栄を享受してきました。それは、多くの先人の汗と涙、そして血の結晶とも言えます。その先人に感謝し、よりよい社会を子孫へ残すという報恩感謝の心掛けこそが、今後のわが国の繁栄に不可欠です。とりわけ国のために戦い、あるいは戦火の犠牲となった先人への感謝と慰霊は重要です。しかし、終戦から80年を迎えてもなお、国家護持の慰霊施設がなく、戦歿者の慰霊は不十分です。戦歿者の慰霊問題を2回に分けて論じます。
3面 天録時評 「経済を守るため脱炭素政策の緩和が必須
わが国は、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目標に、高額な予算を投入して脱炭素政策に邁進しています。一方、脱炭素を積極的に呼びかけていた欧米諸国は、自国の経済状況等を踏まえて脱炭素政策を緩和しています。わが国は、二酸化炭素の排出量を9割以上も抑えることのできる高性能の石炭火力技術を持っています。こうした技術を利用し、脱炭素政策を緩和し、実体経済を見据えた安定的なエネルギー供給策に舵を切るべきです。
4.5面 インタビュー「チベット人がチベット人として
チベットの自由を求める戦いを支援する「チベットに関する世界国会議員会議」が6月3日と4日に、衆議院第一議員会館で開催されました。同会議は1994年(平成6年)にインドのニューデリーで初めて開催され、今回で9回目ですが、日本での開催は初めてです。共催した「日本チベット国会議員連盟」の会長で、参議院議員の山谷えりこ氏に、会議の意義や今後の課題について聞きました。
7面 天録時評 「帰化の条件を厳格化せよ
日本に帰化する中国人が増えています。その理由は、わが国は帰化する条件が緩く、医療皆保険や年金制度といった社会保険制度が充実し、安定した生活ができるからであり、わが国への愛国心や忠誠心はないという人が多いようです。そのような中国人が大量に帰化すれば、そうした中国人によって日本社会の価値観や文化が破壊されかねません。わが国の価値観や文化を守り、社会の安寧を維持するためにも、帰化の条件を諸外国並みに厳しくすべきです。
2面 巷 露 「浅学を恥じつつ先人に感謝」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1.2面 天録時評「戦歿者慰霊問題を考える(上)
戦歿者を慰霊する国家護持の施設を
靖国神社が抱える課題の解消に取り組め
怨親平等で敵味方の区別なく慰霊を」
わが国は、昭和20年の大東亜戦争の終結から80年間、戦火に見舞われることなく、平和と繁栄を享受してきました。それは、多くの先人の汗と涙、そして血の結晶とも言えます。その先人に感謝し、よりよい社会を子孫へ残すという報恩感謝の心掛けこそが、今後のわが国の繁栄に不可欠です。とりわけ国のために戦い、あるいは戦火の犠牲となった先人への感謝と慰霊は重要です。しかし、終戦から80年を迎えてもなお、国家護持の慰霊施設がなく、戦歿者の慰霊は不十分です。戦歿者の慰霊問題を2回に分けて論じます。
3面 天録時評 「経済を守るため脱炭素政策の緩和が必須
高性能石炭火力の活用で
エネルギーの安定供給を」
わが国は、2050年までに温室効果ガスの排出実質ゼロを目標に、高額な予算を投入して脱炭素政策に邁進しています。一方、脱炭素を積極的に呼びかけていた欧米諸国は、自国の経済状況等を踏まえて脱炭素政策を緩和しています。わが国は、二酸化炭素の排出量を9割以上も抑えることのできる高性能の石炭火力技術を持っています。こうした技術を利用し、脱炭素政策を緩和し、実体経済を見据えた安定的なエネルギー供給策に舵を切るべきです。
4.5面 インタビュー「チベット人がチベット人として
生きる環境が守られるように」
日本チベット国会議員連盟会長
参議院議員 山谷えりこ氏」
チベットの自由を求める戦いを支援する「チベットに関する世界国会議員会議」が6月3日と4日に、衆議院第一議員会館で開催されました。同会議は1994年(平成6年)にインドのニューデリーで初めて開催され、今回で9回目ですが、日本での開催は初めてです。共催した「日本チベット国会議員連盟」の会長で、参議院議員の山谷えりこ氏に、会議の意義や今後の課題について聞きました。
7面 天録時評 「帰化の条件を厳格化せよ
愛国心・忠誠心なき帰化人は危険」
日本に帰化する中国人が増えています。その理由は、わが国は帰化する条件が緩く、医療皆保険や年金制度といった社会保険制度が充実し、安定した生活ができるからであり、わが国への愛国心や忠誠心はないという人が多いようです。そのような中国人が大量に帰化すれば、そうした中国人によって日本社会の価値観や文化が破壊されかねません。わが国の価値観や文化を守り、社会の安寧を維持するためにも、帰化の条件を諸外国並みに厳しくすべきです。
2面 巷 露 「浅学を恥じつつ先人に感謝」
6面 小児科医の視点④
「子供の熱中症」当堂游/
最新用語89「デジタル時代の防衛最前線
『国家サイバー統括室』」
8面 日本の肖像132 坂本龍馬(補)
「薩長両藩を和解させ、
武力倒幕の砦=薩長同盟を樹立する」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2067号 編集便りNo.478 2025/07/04
各党が参議院選挙の前哨戦と位置づける東京都議選では、有権者の約8割が物価高や賃上げ対策を最も重視する争点として挙げ、各政党も家賃補助や都民税減税、水道料金無償化など、家計支援策が前面に打ち出されていました。今月20日には参議院議員の選挙が行われますが、都議選と同様に物価高や賃上げ対策など国民の生活に直結する政策が争点になると思われます。一方で、国政選挙となれば、国の安全保障政策やエネルギー政策、憲法改正なども重要な争点となってしかるべきです。原子力の積極利用や憲法九条の改正などを実現できる政治家に投票したいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「使用済燃料 中間貯蔵施設計画
中国電力が山口県上関町で調査・検討している使用済燃料の中間貯蔵施設への反対運動が、県や周辺市町、各議会に対して展開されています。あたかも原子力発電所と同様な危険性があると主張しますが、中間貯蔵施設は原子力災害対策重点区域の設定の必要がなく、重大事故発生のおそれのない施設です。こうした反科学的な運動がわが国のエネルギー政策を歪めています。各首長や議員は科学的根拠に基づいた冷静な対応をすべきです。
2面 天録時評 「年金や医療保険制度への信頼を棄損
厚生年金積立金の国民年金への流用や子ども・子育て支援金の保険料上乗せ徴収など、年金や医療保険制度の本来の目的を逸脱した運用が行われています。つぎはぎだらけの制度を抜本改革し、国民の信頼を回復する社会保障と税制度の確立が急務です。
3面 天録時評 「『中国は最大の脅威』と政府は言明せよ
中国の「力」による国際秩序の変更や他国への主権侵害を抑止するには、力に屈しないというわが国の気概を示さなければなりません。中国を仮想敵国として、具体的な部隊運用などの作戦計画を立案し、国家、国民を守るための国防計画を策定すべきです。外交的にも、まずは中国を「脅威」と位置付けて、これまでの対中外交姿勢を転換する第一歩とすべきです。
4・5面 インタビュー「安倍元総理の志を継承する本義は……」
長年にわたり、国政の第一線で活躍し、内閣府特命担当大臣(少子化対策・一億総活躍担当)などを歴任し、保守政治の理念を体現する存在として活躍をした参議院議員の衛藤晟一氏が今期限りで勇退することになりました。そこで、保守政治の在り方や皇室の意義、さらに若い政治家に期待するものなどの今の思いを聞きました。
2面 巷 露 「改憲しなくて大丈夫ですか」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「使用済燃料 中間貯蔵施設計画
反科学的な反対派の主張に冷静な対応を
山口県・上関町」
中国電力が山口県上関町で調査・検討している使用済燃料の中間貯蔵施設への反対運動が、県や周辺市町、各議会に対して展開されています。あたかも原子力発電所と同様な危険性があると主張しますが、中間貯蔵施設は原子力災害対策重点区域の設定の必要がなく、重大事故発生のおそれのない施設です。こうした反科学的な運動がわが国のエネルギー政策を歪めています。各首長や議員は科学的根拠に基づいた冷静な対応をすべきです。
2面 天録時評 「年金や医療保険制度への信頼を棄損
積立金の流用や制度の目的を逸脱するな」
厚生年金積立金の国民年金への流用や子ども・子育て支援金の保険料上乗せ徴収など、年金や医療保険制度の本来の目的を逸脱した運用が行われています。つぎはぎだらけの制度を抜本改革し、国民の信頼を回復する社会保障と税制度の確立が急務です。
3面 天録時評 「『中国は最大の脅威』と政府は言明せよ
中国を仮想敵国とするのは軍事の常識」
中国の「力」による国際秩序の変更や他国への主権侵害を抑止するには、力に屈しないというわが国の気概を示さなければなりません。中国を仮想敵国として、具体的な部隊運用などの作戦計画を立案し、国家、国民を守るための国防計画を策定すべきです。外交的にも、まずは中国を「脅威」と位置付けて、これまでの対中外交姿勢を転換する第一歩とすべきです。
4・5面 インタビュー「安倍元総理の志を継承する本義は……」
参議院議員 元一億総活躍・
少子化担当大臣 衛藤晟一氏」
長年にわたり、国政の第一線で活躍し、内閣府特命担当大臣(少子化対策・一億総活躍担当)などを歴任し、保守政治の理念を体現する存在として活躍をした参議院議員の衛藤晟一氏が今期限りで勇退することになりました。そこで、保守政治の在り方や皇室の意義、さらに若い政治家に期待するものなどの今の思いを聞きました。
2面 巷 露 「改憲しなくて大丈夫ですか」
6面 天録時評 「外国人の不正受験ビジネスが横行
監視体制の強化で国の信用を守れ」
最新用語88「不法滞在やテロを防止する
『電子渡航認証システム』」
7面 レポート 「ポジティブ行動支援で子供が輝く(下)
思い切った業務改革で
『ポジティブ行動支援』研修を深める」
田布施町立田布施西小学校
8面 日本の肖像131 坂本龍馬(下)
「藩から幕府の小さな枠に束縛されず、
日本国の未来を大きく展望する」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2066号 編集便りNo.477 2025/06/20
先月15日、児童のできているところを褒めてやる気を引き出す「ポジティブ行動支援」を導入した教育を行っている山口県の田布施西小学校に取材に行きました。教員が子供を「褒める」行為だけが注目されがちな支援ですが、田布施西小学校では、どんな行動が望ましい行動なのかをきちんと児童に指導した上で、できているところをしっかり褒め、できなくても叱るのではなく「どうすればよいか」をしっかり教えていました。児童はこうした支援のもと、落ち着いて授業を受けていました。こうした支援は、学校だけでなく家庭でも行うことでより効果が発揮されます。多くの学校で取り入れ、保護者にも広がってほしいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「旧姓使用の法制化で家族と国を守れ!
衆議院法務委員会で、選択的夫婦別姓の導入法案が審議されています。立憲民主党と国民民主党がそれぞれの別姓法案を、日本維新の会が別姓とは一線を画す旧姓の通称使用の法制化案を提出し、この三案が同時に議論されています。どれも成立には至らない見通しですが、責任与党である自民党が党内の意見集約ができず、法案提出にも至らなかったことは無責任です。氏の問題は、国民生活はもちろん日本の国家の基本にも関わる問題だけに、慎重な審議が必要としても自民党が結論を先送りしてきたことが夫婦別姓という家族解体法案成立の危機を招いた主因であり、国民の対立を深めています。
2面 天録時評 「培養肉 行政の『対応の遅さ』が実用化の壁
培養肉の実用化は、安全性審査手続きなどが整備されず、実用化が遅れています。わが国の行政は急速な技術の進歩に対応できていません。現実にそぐわない様々な規制が少なからずあり、最新技術の実用化への対応が遅れています。最新技術を速やかに社会に取り込むため、行政部門で専門家を責任者として期限付きに採用することが求められます。
3面 天録時評 「検察は被疑者に不起訴理由の開示を
3年連続で刑法犯の認知件数が増加する中、6割から7割の人が不起訴処分となっています。不起訴の理由が明らかにされない件数も増加しています。理由が「嫌疑なし」(犯罪に関与していない)なのか「起訴猶予」(罪を犯したことは明白)なのかで大きな差があり、被疑者や関係者にとっては大きな問題です。理由が不開示となれば、外部からは検察の手続きが適切なのかどうかも検証できません。被疑者が求めた場合には検察庁は理由開示を原則として、例外的に不開示とするときは不開示理由の明示を義務付けるべきです。
4面 天録時評 「参議院選挙を前に
7月に参議院議員選挙を控えていますが、選挙のたびに問題となるのが近年の投票率の低さです。わが国でも現在の選挙権が与えられるようになるまでには、多くの先人の切実な願いが込められています。また、選挙という制度自体も、戦争や武力に拠ることなく個人の意思を政治に反映できる社会を形成するための方法として、長い時代を経て実現をみた人類の知恵の結晶です。主権者である国民の責務として投票行動に参画しなければなりません。
2面 巷 露 「どうなる習近平独裁政権」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「旧姓使用の法制化で家族と国を守れ!
自民党は保守政党としての責任を果たせ」
衆議院法務委員会で、選択的夫婦別姓の導入法案が審議されています。立憲民主党と国民民主党がそれぞれの別姓法案を、日本維新の会が別姓とは一線を画す旧姓の通称使用の法制化案を提出し、この三案が同時に議論されています。どれも成立には至らない見通しですが、責任与党である自民党が党内の意見集約ができず、法案提出にも至らなかったことは無責任です。氏の問題は、国民生活はもちろん日本の国家の基本にも関わる問題だけに、慎重な審議が必要としても自民党が結論を先送りしてきたことが夫婦別姓という家族解体法案成立の危機を招いた主因であり、国民の対立を深めています。
2面 天録時評 「培養肉 行政の『対応の遅さ』が実用化の壁
期限付き雇用で研究者を責任者に」
培養肉の実用化は、安全性審査手続きなどが整備されず、実用化が遅れています。わが国の行政は急速な技術の進歩に対応できていません。現実にそぐわない様々な規制が少なからずあり、最新技術の実用化への対応が遅れています。最新技術を速やかに社会に取り込むため、行政部門で専門家を責任者として期限付きに採用することが求められます。
3面 天録時評 「検察は被疑者に不起訴理由の開示を
増える一方の不起訴で司法行政は不透明化」
3年連続で刑法犯の認知件数が増加する中、6割から7割の人が不起訴処分となっています。不起訴の理由が明らかにされない件数も増加しています。理由が「嫌疑なし」(犯罪に関与していない)なのか「起訴猶予」(罪を犯したことは明白)なのかで大きな差があり、被疑者や関係者にとっては大きな問題です。理由が不開示となれば、外部からは検察の手続きが適切なのかどうかも検証できません。被疑者が求めた場合には検察庁は理由開示を原則として、例外的に不開示とするときは不開示理由の明示を義務付けるべきです。
4面 天録時評 「参議院選挙を前に
一票の重さを知り、まずは投票行動を!」
7月に参議院議員選挙を控えていますが、選挙のたびに問題となるのが近年の投票率の低さです。わが国でも現在の選挙権が与えられるようになるまでには、多くの先人の切実な願いが込められています。また、選挙という制度自体も、戦争や武力に拠ることなく個人の意思を政治に反映できる社会を形成するための方法として、長い時代を経て実現をみた人類の知恵の結晶です。主権者である国民の責務として投票行動に参画しなければなりません。
2面 巷 露 「どうなる習近平独裁政権」
5面 太平通信③「減税ポピュリズムに警戒せよ」著述家 拝太平
6面 小児科医の視点③
「持続可能な小児医療に向けて」当堂游
7面 レポート 「ポジティブ行動支援で子供が輝く(上)
できているところを褒めてやる気を引き出す」
田布施町立田布施西小学校
8面 日本の肖像130 坂本龍馬(中)
「幕末の時流、気運に乗って覚醒
独自の倒幕維新論に辿り着く」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2065号 編集便りNo.476 2025/06/06
先月26日、沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域で、中国の海洋調査船がわが国の同意を得ずに活動しているのを、第3管区海上保安本部が確認したと報じられました。政府は、中国が尖閣諸島付近で領空、領海侵犯を繰り返しても「遺憾の意」を示すだけです。このような姿勢を続けていては、尖閣はもとより、わが国の主権が堅持できません。中国の軍拡が続く中で、国民生活そして領土、領海を守るためにも憲法改正をして、外交力を強化する必要があります。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「尖閣諸島 中国の実効支配を許すな
尖閣諸島の領有権奪取を目指す中国は、一歩ずつ着実に実効支配に向けた活動を強化しています。今回の海警局のヘリコプターによる領空侵犯は、尖閣上空でのわが国の航空機の自由な飛行を許さないとの方針を示しました。尖閣周辺での漁業のみならず飛行もできないようになれば、わが国の領土だとの主張が国際司法裁判所でも認められない可能性もあります。中国の軍拡が続くことを考えれば、政府は今、ただちに灯台設置などでわが国の有効な支配の強化策を断行しなければなりません。
2面 天録時評 「トランスジェンダー女性
法的には『女』は『生物学的女性』を指すと英国最高裁が明確な判決を下しました。この判決により、英国ではトランスジェンダー女性の女子専用施設の使用が制限されることになりました。また、スポーツ界でも女子競技への参加禁止が発表されました。わが国でも、浴場やトイレ、更衣室などでは生物学的性別に従った利用を法的に義務付けるべきです。
3面 天録時評 「憲法改正は一刻の猶予も許されない
5月3日の憲法記念日に、今年も「『21世紀の日本と憲法』有識者懇談会」(民間憲法臨調)などが主催する公開憲法フォーラムが行われました。昨年秋の衆院選の結果、改憲に賛成の議員が国会発議に必要な定数の3分の2を割り込んだため盛り上がりが心配されましたが、各党代表者によるシンポジウムで憲法9条改正と緊急事態条項の条文化に向けた共同作業に着手する方向で同意が見られたことは一縷の望みをつないだと言えます。後は有言実行あるのみで、国会議員としての責務を果たすべきです。
4面 原子力レポート「第58回原産年次大会
「原子力利用のさらなる加速―新規建設に向けて」を基調テーマとした今年の原産大会では、解決すべき2つ目の課題として取り上げられたのが「サプライチェーン(供給体制)」です。東日本大震災後、既設原子炉の再稼働が遅れるとともに、新増設が長期にわたって中断していることで技術の継承が停滞するなど、わが国のサプライチェーンは綻びを来しており、新規建設の足枷ともなりかねません。そこで、セッション2では現状の認識を共有するとともに、海外の取り組み事例や支援策などについて議論が展開されました。
2面 巷 露 「入国税で観光公害対策を」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「尖閣諸島 中国の実効支配を許すな
灯台設置などで領有権を国際社会に示せ」
尖閣諸島の領有権奪取を目指す中国は、一歩ずつ着実に実効支配に向けた活動を強化しています。今回の海警局のヘリコプターによる領空侵犯は、尖閣上空でのわが国の航空機の自由な飛行を許さないとの方針を示しました。尖閣周辺での漁業のみならず飛行もできないようになれば、わが国の領土だとの主張が国際司法裁判所でも認められない可能性もあります。中国の軍拡が続くことを考えれば、政府は今、ただちに灯台設置などでわが国の有効な支配の強化策を断行しなければなりません。
2面 天録時評 「トランスジェンダー女性
女性専用施設の利用を禁止 英国最高裁
『生物学的女性』が『女性』」
法的には『女』は『生物学的女性』を指すと英国最高裁が明確な判決を下しました。この判決により、英国ではトランスジェンダー女性の女子専用施設の使用が制限されることになりました。また、スポーツ界でも女子競技への参加禁止が発表されました。わが国でも、浴場やトイレ、更衣室などでは生物学的性別に従った利用を法的に義務付けるべきです。
3面 天録時評 「憲法改正は一刻の猶予も許されない
各党共同で条文化作業の着手を急げ」
5月3日の憲法記念日に、今年も「『21世紀の日本と憲法』有識者懇談会」(民間憲法臨調)などが主催する公開憲法フォーラムが行われました。昨年秋の衆院選の結果、改憲に賛成の議員が国会発議に必要な定数の3分の2を割り込んだため盛り上がりが心配されましたが、各党代表者によるシンポジウムで憲法9条改正と緊急事態条項の条文化に向けた共同作業に着手する方向で同意が見られたことは一縷の望みをつないだと言えます。後は有言実行あるのみで、国会議員としての責務を果たすべきです。
4面 原子力レポート「第58回原産年次大会
原子力新規建設の実現に向けて㊦
セッション2 海外事例に学ぶサプライチェーンの課題」
「原子力利用のさらなる加速―新規建設に向けて」を基調テーマとした今年の原産大会では、解決すべき2つ目の課題として取り上げられたのが「サプライチェーン(供給体制)」です。東日本大震災後、既設原子炉の再稼働が遅れるとともに、新増設が長期にわたって中断していることで技術の継承が停滞するなど、わが国のサプライチェーンは綻びを来しており、新規建設の足枷ともなりかねません。そこで、セッション2では現状の認識を共有するとともに、海外の取り組み事例や支援策などについて議論が展開されました。
2面 巷 露 「入国税で観光公害対策を」
5面 大阪・関西万博2025レポート
「未来を切り拓くエネルギーを体感
電事連『電力館 可能性のタマゴたち』」
6面 地域便り 「避けて通れない自衛隊の憲法明記
鹿児島市で第21回公開憲法フォーラム開催」
(鹿児島市)
地域便り 「50年目を迎えた『北方異民族慰霊祭』
(神戸市)
7面 インタビュー 八重山諸島シリーズ④
八重山防衛協会会長・米盛博明氏
「尖閣領有を主張する国主催の集会で
国民の防衛意識涵養を」
8面 日本の肖像129 坂本龍馬(上)
「南国土佐で生まれ育った大自然児が
倒幕維新の大路線を拓く」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2064号 編集便りNo.475 2025/05/16
先頃、国会で日本学術会議を特殊法人化する政府提出法案の審議が行われました。その際、学術会議の一部会員の「この法律が通ることで、これまでとは違う人が入ってくる」と懸念を示した発言が問題視されました。この会員は「文系には政府にすり寄る、かなり右に立っている人が確実にいる。そういう人たちがここに入ってくる。そういう状態を許していいのか考える必要がある」と述べたと言われています。左に偏った思想の持主ばかりで構成された日本学術会議では、センターラインも右に見え、平和や安全、そして繁栄に役立つ研究を阻害しかねません。そんな学術会議は必要ありません。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「政府は新増設のための具体的道筋を示せ
第7次エネルギー基本計画では原子力の位置づけを「可能な限り依存度を低減」から「最大限活用」に転換しましたが、鍵となる原子力発電所の新増設には資金調達や投資回収等の課題が山積しており、実現できなければエネルギー危機という国難に直面することになります。この打開には政治の果たす役割が大きく、国家、国民のため、身体を張ってでも原子力推進に取り組む勇気のある国会議員を応援し、原子力反対派や消極派の議員は落選させるぐらいの国民運動を展開することが避けられません。
2面 天録時評 「戦闘機を守る掩体の建設を急げ
米国からの防衛予算の増額請求は避けられない中で、最新鋭装備品の購入も必要ですが、わが国の防衛強化力に不可欠なのが基地施設の強靭化です。現状の航空基地では、先制攻撃を受ければ瞬く間にわが国の航空戦力が破滅するおそれがあります。戦闘機を守るための掩体(えんたい=軍用機などの装備を敵の攻撃から守る施設)や自衛官の命を守る医療関係の装備品の充実が急務です。
3面 天録時評 「政府は分かりやすい翻訳語創りを
日本人が英語を苦手にしているのは、英語に頼らなくても高度な理論や革新的な技術の開発ができるからです。それは古代からの文化の積み重ねと明治時代に西洋から導入した物や概念を表す言葉を創ってきたからです。わが国の文化を守り、発展させるために、外国語をカタカナに表記するのではなく、翻訳して理解しやすい新たな言葉を創る取り組みが政府に求められます。
4・5面 原子力レポート「第58回原産年次大会
日本原子力産業協会が毎年春に開催している国際会議「第58回原産年次大会」が4月8日~9日、東京国際フォーラムで開催され、政府・自治体・研究機関・電気事業者など国内外から約740人が参加しました。今回の基調テーマは「原子力利用のさらなる加速-新規建設の実現に向けて」。脱炭素電源として、また、電力需要の増大に対応するために世界的に原子力活用の機運が高まる中で、資金調達やサプライチェーン(供給体制)、人材確保・育成などの課題解決のために、海外の先行事例を学びながら議論しました。
2面 巷 露 「新たな米国建設へ」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「政府は新増設のための具体的道筋を示せ
原子力発電 建設が進まなければ国力低下は必須」
第7次エネルギー基本計画では原子力の位置づけを「可能な限り依存度を低減」から「最大限活用」に転換しましたが、鍵となる原子力発電所の新増設には資金調達や投資回収等の課題が山積しており、実現できなければエネルギー危機という国難に直面することになります。この打開には政治の果たす役割が大きく、国家、国民のため、身体を張ってでも原子力推進に取り組む勇気のある国会議員を応援し、原子力反対派や消極派の議員は落選させるぐらいの国民運動を展開することが避けられません。
2面 天録時評 「戦闘機を守る掩体の建設を急げ
防衛力強化に基地施設の強靭化を」
米国からの防衛予算の増額請求は避けられない中で、最新鋭装備品の購入も必要ですが、わが国の防衛強化力に不可欠なのが基地施設の強靭化です。現状の航空基地では、先制攻撃を受ければ瞬く間にわが国の航空戦力が破滅するおそれがあります。戦闘機を守るための掩体(えんたい=軍用機などの装備を敵の攻撃から守る施設)や自衛官の命を守る医療関係の装備品の充実が急務です。
3面 天録時評 「政府は分かりやすい翻訳語創りを
国語を守れ カタカナ語の氾濫は文化破壊」
日本人が英語を苦手にしているのは、英語に頼らなくても高度な理論や革新的な技術の開発ができるからです。それは古代からの文化の積み重ねと明治時代に西洋から導入した物や概念を表す言葉を創ってきたからです。わが国の文化を守り、発展させるために、外国語をカタカナに表記するのではなく、翻訳して理解しやすい新たな言葉を創る取り組みが政府に求められます。
4・5面 原子力レポート「第58回原産年次大会
原子力新規建設の実現に向けて㊤
『原子力の最大限活用』には諸課題解決が必須
セッション1『新規建設に向けて:資金調達と投資回収』」
日本原子力産業協会が毎年春に開催している国際会議「第58回原産年次大会」が4月8日~9日、東京国際フォーラムで開催され、政府・自治体・研究機関・電気事業者など国内外から約740人が参加しました。今回の基調テーマは「原子力利用のさらなる加速-新規建設の実現に向けて」。脱炭素電源として、また、電力需要の増大に対応するために世界的に原子力活用の機運が高まる中で、資金調達やサプライチェーン(供給体制)、人材確保・育成などの課題解決のために、海外の先行事例を学びながら議論しました。
2面 巷 露 「新たな米国建設へ」
6面 天録時評 「家族の一体感を失う夫婦別姓
立憲案では子供の姓の問題は解決しない」
役立つ最新用語87
「有事の際の住民避難を円滑にする
『特定利用空港・港湾』」
7面 インタビュー 八重山諸島シリーズ③
沖縄県与那国町長・糸数健一氏
「台湾有事は他人ごとではない
憲法9条改正を急げ!」
8面 日本の肖像128 福沢諭吉(補)
「明治の世、独自の世界観で
文化活動を展開した異色の思想家」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2063号 編集便りNo.474 2025/05/02
石破政権になって以降、憲法改正の機運は下がったままです。国会では、衆参両院で憲法審査会が開催されていますが、未だに憲法改正国民投票法を巡る諸問題について議論をしている段階で憲法9条の自衛隊明記など、具体的な条文の改正発議に向けた動きにはなっていません。これでは台湾有事の際に日本は台湾防衛に立ち上がらないのではないかと中国に思われてしまいます。そうなれば抑止力は低下し、台湾有事を招いてしまいます。憲法記念日(5月3日)を前に国民が声を上げていくことの必要性を痛感します。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「歴史と伝統を踏まえ、立法府の責任を示せ
国会では衆参両院正副議長の下、各党派の代表者が集まり、皇位の安定継承に関する検討をしています。額賀福志郎衆院議長は、特に緊急を要する皇族数の確保策について今国会中に結論を得たいとしています。安定的な皇位継承に直結する課題だけに、歴史と伝統を踏まえ、立法府として責任を持って早急に総意をまとめてほしいものです。そのためにも、立憲民主党の野田代表に象徴される私論に付き合っている暇はありません。
2面 天録時評 「英語より国語と算数の授業時間増を
令和12年度から小学校、令和13年度から中学校で実施される次期学習指導要領の見直しに向けた中央教育審議会での議論が昨年末から始まりました。現学習指導要領で英語が教科化されたにもかかわらず、英語嫌いの小中学生が増え、成績も低下しています。小学校では英語を教科から外して外国語活動に戻し、中学校では単語数の削減や基本的文法項目に限定するなどの負担軽減が必要です。
3面 天録時評 「大学や研究所からの情報流出の防止を
経済安全保障の観点からも重要な最先端技術の流出防止への取り組みが求められています。中国共産党は米国を追い抜くために最先端技術の入手に躍起となっているだけに警戒が必要です。中国共産党が各国の大学院に、国費で留学生を送り込んでいることから、米国やEUなどでは一層の警戒を強めています。一方、わが国の国立大学は授業料免除などで積極的に受け入れ、警戒心も乏しい状況です。国立大学の中国国籍の副学長も増えており、中国からの国費留学生などの管理体制を整備すべきです。
4・5面 国民大会レポート
安定的皇位継承の法制化を求める国民大会が4月7日、衆議院第一議員会館で開催され、約500人が参加しました。現在、国会では衆参両院正副議長の下、皇族数の確保に向けた各党会派の検討がされており、国民大会はその合意形成を後押しするものです。要望書案を採択し、各党代表者に手渡しました。
2面 巷 露 「トランプ関税は入場料」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「歴史と伝統を踏まえ、立法府の責任を示せ
皇族数確保 立憲・野田私論には毅然と対処を」
国会では衆参両院正副議長の下、各党派の代表者が集まり、皇位の安定継承に関する検討をしています。額賀福志郎衆院議長は、特に緊急を要する皇族数の確保策について今国会中に結論を得たいとしています。安定的な皇位継承に直結する課題だけに、歴史と伝統を踏まえ、立法府として責任を持って早急に総意をまとめてほしいものです。そのためにも、立憲民主党の野田代表に象徴される私論に付き合っている暇はありません。
2面 天録時評 「英語より国語と算数の授業時間増を
学習指導要領の見直し
英語嫌いが増え基礎学力も低下」
令和12年度から小学校、令和13年度から中学校で実施される次期学習指導要領の見直しに向けた中央教育審議会での議論が昨年末から始まりました。現学習指導要領で英語が教科化されたにもかかわらず、英語嫌いの小中学生が増え、成績も低下しています。小学校では英語を教科から外して外国語活動に戻し、中学校では単語数の削減や基本的文法項目に限定するなどの負担軽減が必要です。
3面 天録時評 「大学や研究所からの情報流出の防止を
中国からの国費留学生
最先端分野での受け入れ禁止が急務」
経済安全保障の観点からも重要な最先端技術の流出防止への取り組みが求められています。中国共産党は米国を追い抜くために最先端技術の入手に躍起となっているだけに警戒が必要です。中国共産党が各国の大学院に、国費で留学生を送り込んでいることから、米国やEUなどでは一層の警戒を強めています。一方、わが国の国立大学は授業料免除などで積極的に受け入れ、警戒心も乏しい状況です。国立大学の中国国籍の副学長も増えており、中国からの国費留学生などの管理体制を整備すべきです。
4・5面 国民大会レポート
「皇族数確保に向けた合意形成を後押し
安定的皇位継承の法制化を求める国民大会
4月7日」
安定的皇位継承の法制化を求める国民大会が4月7日、衆議院第一議員会館で開催され、約500人が参加しました。現在、国会では衆参両院正副議長の下、皇族数の確保に向けた各党会派の検討がされており、国民大会はその合意形成を後押しするものです。要望書案を採択し、各党代表者に手渡しました。
2面 巷 露 「トランプ関税は入場料」
6面 小児科医の視点②
「五歳児検診の意義と展望」
役立つ最新用語86
「離島での迅速な部隊輸送を可能にする
『自衛隊海上輸送群』」
7面 インタビュー 八重山諸島シリーズ②
沖縄県竹富町長・前泊正人氏
「災害や有事の際の住民移動に関する
態勢強化が必須」
8面 日本の肖像127 福沢諭吉(下)
「新しい教育機関として大学を創り、
入門書『学問ノススメ』を奨励」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2062号 編集便りNo.473 2025/04/18
「台湾有事は日本の有事」と言われて久しいですが、国民にその危機感が共有できているとは言い難いです。そこで、今号からで国境の島・八重山諸島の首長らに国境の島の現状を聞き、4回シリーズで掲載することとしました。第一回目は中山義隆石垣市長で、「八重山諸島は国防としての安全保障はもちろん、食料安全保障、エネルギー安全保障上でも重要なシーレーンに一番近いところに位置している。この島々があるからこそ食料やエネルギーの供給が安定的にできていると言っても過言ではない」の言葉の重みに胸を打たれました。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「原子力“忌避”で国益無視の朝日社説
日本原子力文化財団の世論調査で「原子力発電をどのように利用していけばよいか」の問いに3割超が「わからない」と答え、特に若年層での増加が目立ったようです。原因として「情報過多」や「どの情報を信じてよいか分からない」などが挙がったと言いますが、まるで他人事です。2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画に対する新聞各紙の社説を比較しつつ、それでも甘い認識であることを指摘し、もはや原子力“忌避”では済まされない実情を訴えています。
2面 天録時評 「無責任な水産行政が漁業衰退を招く
かつて世界一だったわが国の漁獲高は、令和5年で12位となり、一方で水産物の輸入量は世界一になりました。サバやスルメイカをはじめ、多くの魚で漁獲量が激減しています。資源管理制度の不備が原因であり、水産行政こそが漁業衰退を招く元凶となっています。国民の財産でもある水産資源の回復のためには、厳格な資源管理こそが急がれます。
3面 天録時評 「防衛産業を再編統合し開発研究力の強化を
第2次トランプ政権による自動車への追加関税や相互関税は、わが国の経済にも深刻な打撃を与えるのは必至です。経済の落ち込みをできるだけ少なくするためには、安全保障環境が厳しさを増している今こそ、裾野の広い国防産業の育成を重点施策とすべきです。わが国の優れた民生技術の取り込みやAI(人工知能)を活用した新たな兵器の研究開発など、自主、自律的な防衛力強化に国を挙げての取り組みが求められます。米国の言いなりに米国製の装備品を購入するのではなく、わが国に相応しい兵器開発をすることこそが、国防力の基盤整備に繋がるとともに、わが国の経済の成長にも貢献できます。
4・5面インタビュー 八重山諸島シリーズ①
中国による度重なる尖閣諸島付近での領海侵犯など、近年、奄美諸島及び沖縄の宮古・八重山諸島を取り巻く安全保障環境は厳しい状況に置かれています。さらには、南海トラフ地震による津波被害なども想定されています。こうした背景から、有事の際の国防体制の構築はもとより、災害時の離島住民の避難体制の構築も急務です。そこで、中山義隆石垣市長に国防最前線の離島の防衛体制の現状を聞きました。
2面 巷 露 「握手よりも政策を」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「原子力“忌避”で国益無視の朝日社説
原子力“回帰”の基本計画でも厳しい現実
エネルギー政策」
日本原子力文化財団の世論調査で「原子力発電をどのように利用していけばよいか」の問いに3割超が「わからない」と答え、特に若年層での増加が目立ったようです。原因として「情報過多」や「どの情報を信じてよいか分からない」などが挙がったと言いますが、まるで他人事です。2月に閣議決定した第7次エネルギー基本計画に対する新聞各紙の社説を比較しつつ、それでも甘い認識であることを指摘し、もはや原子力“忌避”では済まされない実情を訴えています。
2面 天録時評 「無責任な水産行政が漁業衰退を招く
国民の共有財産である水産資源保護を急げ」
かつて世界一だったわが国の漁獲高は、令和5年で12位となり、一方で水産物の輸入量は世界一になりました。サバやスルメイカをはじめ、多くの魚で漁獲量が激減しています。資源管理制度の不備が原因であり、水産行政こそが漁業衰退を招く元凶となっています。国民の財産でもある水産資源の回復のためには、厳格な資源管理こそが急がれます。
3面 天録時評 「防衛産業を再編統合し開発研究力の強化を
防衛装備品の生産力向上が急務
トランプ関税」
第2次トランプ政権による自動車への追加関税や相互関税は、わが国の経済にも深刻な打撃を与えるのは必至です。経済の落ち込みをできるだけ少なくするためには、安全保障環境が厳しさを増している今こそ、裾野の広い国防産業の育成を重点施策とすべきです。わが国の優れた民生技術の取り込みやAI(人工知能)を活用した新たな兵器の研究開発など、自主、自律的な防衛力強化に国を挙げての取り組みが求められます。米国の言いなりに米国製の装備品を購入するのではなく、わが国に相応しい兵器開発をすることこそが、国防力の基盤整備に繋がるとともに、わが国の経済の成長にも貢献できます。
4・5面インタビュー 八重山諸島シリーズ①
沖縄県石垣市長 中山義隆氏
「国防最前線の離島の防衛体制に理解を
有事に島民の命を守る避難体制構築が急務」
中国による度重なる尖閣諸島付近での領海侵犯など、近年、奄美諸島及び沖縄の宮古・八重山諸島を取り巻く安全保障環境は厳しい状況に置かれています。さらには、南海トラフ地震による津波被害なども想定されています。こうした背景から、有事の際の国防体制の構築はもとより、災害時の離島住民の避難体制の構築も急務です。そこで、中山義隆石垣市長に国防最前線の離島の防衛体制の現状を聞きました。
2面 巷 露 「握手よりも政策を」
6面 太平通信②「次世代のために投資せよ」著述家 拝太平
7面 天録時評 「『浮体式原子力発電』に注目を
新型炉開発は選択と集中が必須」
役立つ最新用語85
「水道水からも検出される『PFAS』」
8面 日本の肖像126
明治の世を新開拓の文学で導く 福沢諭吉(中)
「ドイツに倣う新政府に付かず離れず、
英米中心の文明開化の道を拓く」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2061号 編集便りNo.472 2025/04/04
先月25日、大阪高裁は、同性婚を認めていない現行の民法や戸籍法の規定について「違憲」との判断を示しました。その際、憲法24条の趣旨は明治民法と決別することにあり、同性婚を排除するものではなく、婚姻は互いに求め合う人にとって「幸福追求のための重要な選択肢」と位置づけました。こうした判決を受けて同性婚を法制化すれば、今後も「幸福追求」の名のもとに一夫多妻、親族兄弟による結婚など多様な結婚の形をすべて認めざるを得なくなるおそれさえないとは言えません。現在の婚姻制度を崩しかねない同性婚は法制化すべきではありません。それでは紙面案内です。(田村)
1・2面 天録時評「自衛官の答弁を認め、文民統制の重責果たせ
わが国が大きな恩恵を受けてきた国際秩序が失われ、世界は混迷を深めています。国防、外交政策だけでなくエネルギーや食料などの安全保障政策の舵取りの重要性が増しています。国際潮流を読み、わが国の進路を誤らないためには、国会議員は重責を自覚し、見識を高めなければなりません。なかでも文民統制を実効あるものにするためには、自衛官に国会答弁をさせないという悪しき慣例を廃止し、国民の負託に応える真摯な安保論議を行うべきです。
3面 天録時評 「パチンコや公営賭博のテレビCM禁止を
わが国では違法であるオンラインカジノに興じ、検挙される人が増加しています。その要因の一つは、オンラインカジノが違法であるという認識不足にあると言われていますが、パチンコの換金や、競馬や競輪などの公営ギャンブルが堂々と行われている環境では、罪悪感や警戒感が薄れるのも当然と言えます。賭博による犯罪行為やギャンブル依存症患者を抑制するには、オンラインカジノの摘発強化だけでなく、賭博を奨励するパチンコや公営ギャンブルのテレビCMの禁止こそ最優先で取り組むべきです。
4・5面 国民集会レポート 3月12日
3月12日、日本社会の根幹に関わる夫婦の氏(姓)の在り方について考える国民集会が衆議院第1議員会館で開催されました。自民党をはじめ、日本維新の会、参政党、日本保守党から代理を含めて75人の国会議員が参加しました。「同姓の原則を堅持しつつ、社会生活上の不便不利益の解消」「『旧姓の通称使用法』(仮称)を制定」を求める要望書を採決しました。
6面 地域便り 3月1日、笠松小で
岐阜県内で「心の通う子を育てる道徳教育の実践」を進める学校を激励する岐阜県道徳教育奨励賞受賞式が、今年で20年目を迎えました。今年度は27校の応募があり、笠松町立笠松小学校が最優秀賞として選ばれました。20周年という節目の年を迎え、令和7年3月1日(土)に過去最多の参加実績のある笠松小学校を会場に、全学年全クラス一斉の道徳公開授業及び表彰式が実施されました。
2面 巷 露 「怖いスマホ依存」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1・2面 天録時評「自衛官の答弁を認め、文民統制の重責果たせ
国会議員は国家安寧を守るための高い見識が必須」
わが国が大きな恩恵を受けてきた国際秩序が失われ、世界は混迷を深めています。国防、外交政策だけでなくエネルギーや食料などの安全保障政策の舵取りの重要性が増しています。国際潮流を読み、わが国の進路を誤らないためには、国会議員は重責を自覚し、見識を高めなければなりません。なかでも文民統制を実効あるものにするためには、自衛官に国会答弁をさせないという悪しき慣例を廃止し、国民の負託に応える真摯な安保論議を行うべきです。
3面 天録時評 「パチンコや公営賭博のテレビCM禁止を
違法と認識せず興じるオンラインカジノ」
わが国では違法であるオンラインカジノに興じ、検挙される人が増加しています。その要因の一つは、オンラインカジノが違法であるという認識不足にあると言われていますが、パチンコの換金や、競馬や競輪などの公営ギャンブルが堂々と行われている環境では、罪悪感や警戒感が薄れるのも当然と言えます。賭博による犯罪行為やギャンブル依存症患者を抑制するには、オンラインカジノの摘発強化だけでなく、賭博を奨励するパチンコや公営ギャンブルのテレビCMの禁止こそ最優先で取り組むべきです。
4・5面 国民集会レポート 3月12日
「家族と子供を守るために夫婦同姓の維持を
『旧姓の通称使用』の法制化を求める国民集会」
3月12日、日本社会の根幹に関わる夫婦の氏(姓)の在り方について考える国民集会が衆議院第1議員会館で開催されました。自民党をはじめ、日本維新の会、参政党、日本保守党から代理を含めて75人の国会議員が参加しました。「同姓の原則を堅持しつつ、社会生活上の不便不利益の解消」「『旧姓の通称使用法』(仮称)を制定」を求める要望書を採決しました。
6面 地域便り 3月1日、笠松小で
「20年目を迎えた岐阜県道徳教育奨励賞
地域とともに道徳教育を進める素晴らしさを実感」
岐阜県内で「心の通う子を育てる道徳教育の実践」を進める学校を激励する岐阜県道徳教育奨励賞受賞式が、今年で20年目を迎えました。今年度は27校の応募があり、笠松町立笠松小学校が最優秀賞として選ばれました。20周年という節目の年を迎え、令和7年3月1日(土)に過去最多の参加実績のある笠松小学校を会場に、全学年全クラス一斉の道徳公開授業及び表彰式が実施されました。
2面 巷 露 「怖いスマホ依存」
7面 小児科医の視点①
「子供と家族を日本のまんなかに」当堂游
役立つ最新用語84
「高放射線量下でも作動する
『ダイヤモンド半導体』」
8面 太平通信①
「国民皆保険を考える」
著述家 拝太平
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2060号 編集便りNo.471 2025/03/21
令和7年度の予算案が衆議院を通過し、高校授業料無償化政策が4月から始まります。この政策により、特に都市部では有名私立高校への入学希望者が増え、公立高校は定員割れが加速化すると懸念されています。福岡県でも定員ギリギリの公立高校が多数存在し、もし3年連続で定員割れになった学校は再編対象となるという「大阪ルール」が適用されれば、多くの公立高校で統廃合が進み、近くに通う高校がないという生徒が多数発生すると指摘されています。公教育を崩壊しかねない所得制限なしの高校授業料無償化は見直すべきです。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「柏崎刈羽 特重施設とは切り離して再稼働を
東京電力・柏崎刈羽原子力発電所7号機の再稼働の時期が実質的に3、4年遅れることになりました。原子炉の安全性とは直接関係のない特定重大事故等対処施設の完成が遅れるためです。エネルギー安全保障や国民生活を守る観点から、政府は特重施設の建設と再稼働を切り離すことを決定すべきです。また、専門人材の不足から審査が遅れている原子力規制委員会に電力会社からの出向も容認すべきです。
2面 天録時評 「中学校公民教科書
個人主義的価値観が蔓延する昨今、中学校公民教科書の家族に関する記述は、先祖を敬い、家族の絆を大切にし、道徳心や倫理意識、文化を子孫に継承するといった家族が果たす役割の記述が少なくなっています。家族の大切さを認識するためには、自由社のように先祖―自分―子孫という時間的な縦のつながりを明記した教科書を採択し、子供たちに学ばせなければなりません。
3面 インタビュー「陛下をお支えする男系男子皇族の存在が重要
衆参両院の正副議長と各党・各派の代表者らによる、安定的な皇位継承に関する与野党協議は、今国会中に一定の結論を出すことで一致しているといいます。中でも、皇族数の確保策は喫緊の課題です。そこで、皇室関係に詳しい和田政宗参議院議員に安定的な皇位継承に取り組んでいくことの意義について聞きました。
6面 天録時評 「弊害が大きい所得制限なしの高校無償化
高校授業料の無償化が予算案通過のための政争の具とされました。教育を受ける側の負担の軽減化のみに焦点が当たっていますが、その効果も大きくありません。無償化の財源は増税によって国民が負担しなければなりません。公金投入の緊急性があるのは、AI(人工知能)の活用が進む中で、教育の質の転換や向上であり、それを担う教育する側への投資が不可欠です。
2面 巷 露 「デフレ脱却の決定打」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「柏崎刈羽 特重施設とは切り離して再稼働を
再稼働の遅れは原子力規制委員会の人材不足」
東京電力・柏崎刈羽原子力発電所7号機の再稼働の時期が実質的に3、4年遅れることになりました。原子炉の安全性とは直接関係のない特定重大事故等対処施設の完成が遅れるためです。エネルギー安全保障や国民生活を守る観点から、政府は特重施設の建設と再稼働を切り離すことを決定すべきです。また、専門人材の不足から審査が遅れている原子力規制委員会に電力会社からの出向も容認すべきです。
2面 天録時評 「中学校公民教科書
家族は『協力』『責任感』『一体感』を育む場
家族を大切にする自由社の教科書記述」
個人主義的価値観が蔓延する昨今、中学校公民教科書の家族に関する記述は、先祖を敬い、家族の絆を大切にし、道徳心や倫理意識、文化を子孫に継承するといった家族が果たす役割の記述が少なくなっています。家族の大切さを認識するためには、自由社のように先祖―自分―子孫という時間的な縦のつながりを明記した教科書を採択し、子供たちに学ばせなければなりません。
3面 インタビュー「陛下をお支えする男系男子皇族の存在が重要
参議院議員内閣委員長 和田政宗氏」
衆参両院の正副議長と各党・各派の代表者らによる、安定的な皇位継承に関する与野党協議は、今国会中に一定の結論を出すことで一致しているといいます。中でも、皇族数の確保策は喫緊の課題です。そこで、皇室関係に詳しい和田政宗参議院議員に安定的な皇位継承に取り組んでいくことの意義について聞きました。
6面 天録時評 「弊害が大きい所得制限なしの高校無償化
公教育の質の低下や中学受験の激化を招く」
高校授業料の無償化が予算案通過のための政争の具とされました。教育を受ける側の負担の軽減化のみに焦点が当たっていますが、その効果も大きくありません。無償化の財源は増税によって国民が負担しなければなりません。公金投入の緊急性があるのは、AI(人工知能)の活用が進む中で、教育の質の転換や向上であり、それを担う教育する側への投資が不可欠です。
2面 巷 露 「デフレ脱却の決定打」
4・5面レポート「第20回『竹島の日』記念式典
2月22日開催
進展が見られない現状に憤りの声も」
7面 天録時評 「何でも相談できる親子関係の構築を
オンラインゲームに潜む犯罪の危険」
役立つ最新用語83
「闇バイト強盗の抑止につながる
『仮装身分捜査』」
8面 日本の肖像125
明治の世を新開拓の文学で導く 福沢諭吉(上)
「漢学から蘭学、蘭学から英語中心へ
新しい学問を手探りで切り拓く」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2059号 編集便りNo.470 2025/03/07
ミャンマーを舞台にして国際的な詐欺が行われており、日本人の高校生も詐欺に加担させられていました。きっかけはオンラインゲームで、ゲームで知り合った日本人の男から「むこうに行くと良い仕事がある」などと誘われたということでした。わが高校生の息子も、友達とは思えない人と会話をしながらオンラインゲームをしています。犯罪に巻き込まれないようにするには、ゲーム内で知り合った人と安易に連絡先の交換をしない、実際に会わない、少しでも不安を感じたら相談するなどの家庭内でのルールを作ることが必要だと改めて感じました。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「『竹島の日』記念式典に思う
令和7年2月22日、島根県主催による「竹島の日」記念式典(竹島・北方領土返還要求運動県民大会)が開かれました。島根県知事は、政府主催での式典開催を要請していますが、20回目の節目となった今年の式典でも叶わず、政府閣僚の出席すらありませんでした。日韓関係の緊張を避けるためとのことですが、こうした弱腰姿勢では領土返還の進展は望めません。
2面 天録時評 「政策立案できる政策研究所が必要
わが国の国家運営は、省中心の官僚組織に依存してきました。継続性や前例踏襲主義、あるいは無謬性に固執しやすい官僚組織では、世界の急激な変化への対応や既得権益を壊すような政策立案は困難です。現状を打破して、国民生活を豊かにするためには、的確な現状分析に基づく政策を提示できる政策研究所(シンクタンク)を政党が持つ必要性が高まっています。
3面 天録時評 「消費税 国民が納得できる税に再設計を
消費税は消費者が負担する間接税のように説明されていますが、事業者を納税義務者とする直接税です。社会福祉目的税と言われますが、一般会計に繰り入れられて何にでも使えます。しかも、米国が問題としているように輸出補助金的な役割を果たしています。もともと低所得者の負担が大きい逆進性や税の応能負担原則に反しているなどの欠陥が指摘されています。食料品などを非課税とし、贅沢品に高率を課す間接税として再設計すべきです。
6・7面 地域便り「各地で建国記念の日を祝う式典が開催
令和7年、皇紀2685年の2月11日、建国記念の日を祝う奉祝行事が各地で行われ、参加者こぞって建国記念の日を祝いました。今年は戦後80年、昭和100年の節目の年でもあり、世界が自分中心、自国中心主義に向かう中、改めてわが国の悠久の歴史に思いをいたし、日本国民の高い道徳性に誇りを持ち、公を重んじる態度を涵養することの必要性を訴える講演会などが各地で催されました。その奉祝式典などの様子を紹介します。
2面 巷 露 「貸付は貨幣の創造」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「『竹島の日』記念式典に思う
『領土を守る』意志を毅然と行動で示せ!
弱腰姿勢では一歩も前進しない」
令和7年2月22日、島根県主催による「竹島の日」記念式典(竹島・北方領土返還要求運動県民大会)が開かれました。島根県知事は、政府主催での式典開催を要請していますが、20回目の節目となった今年の式典でも叶わず、政府閣僚の出席すらありませんでした。日韓関係の緊張を避けるためとのことですが、こうした弱腰姿勢では領土返還の進展は望めません。
2面 天録時評 「政策立案できる政策研究所が必要
弊害が目立つ官僚依存の政治運営」
わが国の国家運営は、省中心の官僚組織に依存してきました。継続性や前例踏襲主義、あるいは無謬性に固執しやすい官僚組織では、世界の急激な変化への対応や既得権益を壊すような政策立案は困難です。現状を打破して、国民生活を豊かにするためには、的確な現状分析に基づく政策を提示できる政策研究所(シンクタンク)を政党が持つ必要性が高まっています。
3面 天録時評 「消費税 国民が納得できる税に再設計を
詐欺やごまかしの不都合な真実が明るみに」
消費税は消費者が負担する間接税のように説明されていますが、事業者を納税義務者とする直接税です。社会福祉目的税と言われますが、一般会計に繰り入れられて何にでも使えます。しかも、米国が問題としているように輸出補助金的な役割を果たしています。もともと低所得者の負担が大きい逆進性や税の応能負担原則に反しているなどの欠陥が指摘されています。食料品などを非課税とし、贅沢品に高率を課す間接税として再設計すべきです。
6・7面 地域便り「各地で建国記念の日を祝う式典が開催
公を重んじる教育の必要性を訴える講演も」
令和7年、皇紀2685年の2月11日、建国記念の日を祝う奉祝行事が各地で行われ、参加者こぞって建国記念の日を祝いました。今年は戦後80年、昭和100年の節目の年でもあり、世界が自分中心、自国中心主義に向かう中、改めてわが国の悠久の歴史に思いをいたし、日本国民の高い道徳性に誇りを持ち、公を重んじる態度を涵養することの必要性を訴える講演会などが各地で催されました。その奉祝式典などの様子を紹介します。
2面 巷 露 「貸付は貨幣の創造」
4面インタビュー「家族や戸籍の重要性を再認識し、
日本の国柄を守ろう」
元拉致担当大臣(参議院議員)山谷えり子氏
5面インタビュー「戸籍制度の重みを理解した上で慎重に議論を」
自民党「氏の在り方ワーキングチーム」
元座長・石原伸晃氏
8面 日本の肖像124 帝国軍人の模範となる 乃木希典(補)
「決死の突撃戦で形勢を逆転
日露戦争を勝利に導く」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2058号 編集便りNo.469 2025/02/21
2月11日の建国記念の日、私が住む山口市では、コロナ禍後ようやく奉祝パレードが復活しました。報道陣の姿もあったので、パレードや奉祝式典の記事が載っているだろうと期待して翌日の読売新聞の地方面を見ましたが、建国記念の日への反対集会の記事のみが掲載されていました。祝日法には、建国をしのび、国を愛する心を養うとありますが、新聞が反対集会のみを報じたのでは愛国心は養えません。愛国心を否定する記事しか掲載しない新聞は購読の価値がありません。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「社会を破滅させる立憲の夫婦別姓制度
昨年の11月、立憲民主党の野田佳彦代表は、衆院法務委員長のポストを確保したのは選択的夫婦別姓の実現が狙いで、「自民党を揺さぶるには非常に効果的」と語りました。わが国社会に多大な影響を与える夫婦の氏の問題を政争の具にする一点で、野田氏が保守政治家でないことは明白です。選択的夫婦別姓導入は、自民党にとって自殺行為であることを改めて警告します。
2面 天録時評 「米生産の拡大へ政策転換を
農水省は水田を畑地に転換させ、米の生産量を削減する減反政策を続けています。これでは天候異変があれば供給量は不足するし、有事の際には食料難に陥ります。2030年には個人経営の米作農家は半減し、東北地方の農地面積を上回る92万ヘクタールの耕作放棄地になると農水省自体が予測しています。食料安保に逆行している米政策の大転換が急務です。
3面 天録時評 「原子力の平和利用
危険性が存在しないことを安全と考える国民が少なくありません。しかし、リスク(好ましくない事象が起こる可能性とその影響)がゼロの絶対安全は存在しません。豊かな社会を目指すためには安全やリスクの正しい理解が必要です。人類が火への恐怖を克服したように、われわれは放射線や原子力発電の仕組みを正しく理解して、本能的な恐怖心を克服することが求められています。
6面 天録時評 「未だに残る“政治起源説”に基づく歴史記述
歴史研究においても新たな古文書や史料が発見され、通説が書き換えられています。「士農商工」は江戸時代の身分制度とされていましたが、今では「すべての人々」を指す言葉として教科書から消えました。「えた・ひにん」などの部落差別の起原を、徳川幕府が農民などの不満を幕政から逸らすために作ったとする近世政治起源説も学術的に否定されつつあります。同和教育の是正のためにも正しい記述の歴史教科書の採択が求められます。
2面 巷 露 「増加する自閉症児」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「社会を破滅させる立憲の夫婦別姓制度
自民党 導入すれば保守政党としての自殺行為」
昨年の11月、立憲民主党の野田佳彦代表は、衆院法務委員長のポストを確保したのは選択的夫婦別姓の実現が狙いで、「自民党を揺さぶるには非常に効果的」と語りました。わが国社会に多大な影響を与える夫婦の氏の問題を政争の具にする一点で、野田氏が保守政治家でないことは明白です。選択的夫婦別姓導入は、自民党にとって自殺行為であることを改めて警告します。
2面 天録時評 「米生産の拡大へ政策転換を
食料安保に逆行する減反政策を廃止せよ」
農水省は水田を畑地に転換させ、米の生産量を削減する減反政策を続けています。これでは天候異変があれば供給量は不足するし、有事の際には食料難に陥ります。2030年には個人経営の米作農家は半減し、東北地方の農地面積を上回る92万ヘクタールの耕作放棄地になると農水省自体が予測しています。食料安保に逆行している米政策の大転換が急務です。
3面 天録時評 「原子力の平和利用
安全とリスクの正しい理解を
事故の発生確率を低減し安全性の向上へ」
危険性が存在しないことを安全と考える国民が少なくありません。しかし、リスク(好ましくない事象が起こる可能性とその影響)がゼロの絶対安全は存在しません。豊かな社会を目指すためには安全やリスクの正しい理解が必要です。人類が火への恐怖を克服したように、われわれは放射線や原子力発電の仕組みを正しく理解して、本能的な恐怖心を克服することが求められています。
6面 天録時評 「未だに残る“政治起源説”に基づく歴史記述
誤った歴史認識からの脱却を教員側から」
歴史研究においても新たな古文書や史料が発見され、通説が書き換えられています。「士農商工」は江戸時代の身分制度とされていましたが、今では「すべての人々」を指す言葉として教科書から消えました。「えた・ひにん」などの部落差別の起原を、徳川幕府が農民などの不満を幕政から逸らすために作ったとする近世政治起源説も学術的に否定されつつあります。同和教育の是正のためにも正しい記述の歴史教科書の採択が求められます。
2面 巷 露 「増加する自閉症児」
4・5面講演録 「いずみ会東京班・新春勉強会より
昭和100年・終戦80年
『皇室のご聖徳を仰ぐ』(下)
世界最古の元首としての伝統を体現」
7面 天録時評 「中国人に悪用される外免切替
不動産所有など対中外交は相互主義を貫け」
役立つ最新用語82
「自律的に行動する『AIエージェント』」
8面 日本の肖像123 帝国軍人の模範となる 乃木希典(下)
「ドイツ軍人の忠誠心、質実剛健に感銘し、
帝国軍人の範となる決意を固める」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2057号 編集便りNo.468 2025/02/07
1月24日に召集された通常国会の施政方針演説で、石破総理は「楽しい国を目指す」と述べました。しかし、ガソリン代も電気代も物価も高騰し、税金などの国民負担ばかりが増えています。「103万円の壁」と言われる所得控除やガソリン税等の見直し、公共投資の拡大など国家・国民を豊かにする施策を断行してほしいものです。それでは紙面案内です。(田村)
1・2面 天録時評「自国通貨建て国債 わが国の財政破綻はない
わが国経済の長期低迷は、官民の投資不足が大きな要因の一つです。それを招いた原因に、財務省の財政健全主義に政治も経済専門家もマスコミも縛られ、消極的な財政運営を続けたことがあります。しかも財務省は、国家財政と家計を同一視し、財政赤字が増えれば国家財政が破綻すると国民を脅すなど、経済理論を捻じ曲げて国民を委縮させ、貧困化を招きました。財政によって国民を豊かにするのが政治の役割、責任であり、経済や財政理論の正しい理解に基づき、国民の生命や生活を守るための政策実現には、これまでの財務省主導の財政運営の大転換が必要です。
3面 天録時評 「建国記念の日 由来を知り、感謝の心の涵養を
わが国が平和で安定した治安の下、国民が豊かな生活を享受できているのは、国家があり先人先祖が平和な世の中を維持する努力をしてきたからです。2月11日の「建国記念の日」を迎えるにあたり、その建国の由来や意味を今一度振り返り、国民の祝日に関する法律(祝日法)に掲げる「建国をしのび、国を愛する心を養う」一助としたいと思います。同時に、その心の発露として建国記念の日に各家庭で国旗を掲げて祝意を示すことを呼びかけます。
4・5面 講演録「いずみ会東京班・新春勉強会より
『日本時事評論』の支援団体「いずみ会」の東京班が、新年最初の行事として、国会議事堂の見学会と併せて皇室に関する勉強会を開催しました。勉強会では、平沼正二郎衆議院議員秘書の福井慎二氏が「皇室のご聖徳を仰ぐ」と題して講演しました。昭和100年、終戦80年の節目に皇室や英霊について振り返るべく、講演要旨を紹介します。
6面 天録時評 「教育基本法の目標に沿う教育振興基本計画を
教育基本法が改正されて19年が経ちます。この間、国や地方自治体は教育基本法に掲げられた「教育振興基本計画」を策定し、教育活動を行ってきました。しかし、その実態は「道徳心を培う」や「わが国の郷土を愛する」などの教育基本法の目標が十分に反映されているとは言い難いものです。また、教育施策の評価についても評価基準や方法が明示されておらず不十分です。国民に教育基本法改正の意義を広めるためにも、評価の基準と結果を公表すべきです。
2面 巷 露 「落ち続ける月」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1・2面 天録時評「自国通貨建て国債 わが国の財政破綻はない
経済の長期低迷を招いた
財務省主導財政の大転換を」
わが国経済の長期低迷は、官民の投資不足が大きな要因の一つです。それを招いた原因に、財務省の財政健全主義に政治も経済専門家もマスコミも縛られ、消極的な財政運営を続けたことがあります。しかも財務省は、国家財政と家計を同一視し、財政赤字が増えれば国家財政が破綻すると国民を脅すなど、経済理論を捻じ曲げて国民を委縮させ、貧困化を招きました。財政によって国民を豊かにするのが政治の役割、責任であり、経済や財政理論の正しい理解に基づき、国民の生命や生活を守るための政策実現には、これまでの財務省主導の財政運営の大転換が必要です。
3面 天録時評 「建国記念の日 由来を知り、感謝の心の涵養を
各家庭で国旗を掲揚して祝意を表そう」
わが国が平和で安定した治安の下、国民が豊かな生活を享受できているのは、国家があり先人先祖が平和な世の中を維持する努力をしてきたからです。2月11日の「建国記念の日」を迎えるにあたり、その建国の由来や意味を今一度振り返り、国民の祝日に関する法律(祝日法)に掲げる「建国をしのび、国を愛する心を養う」一助としたいと思います。同時に、その心の発露として建国記念の日に各家庭で国旗を掲げて祝意を示すことを呼びかけます。
4・5面 講演録「いずみ会東京班・新春勉強会より
昭和100年・終戦80年
『皇室のご聖徳を仰ぐ』(上)
常に国民の安寧と国土安泰を祈られる」
『日本時事評論』の支援団体「いずみ会」の東京班が、新年最初の行事として、国会議事堂の見学会と併せて皇室に関する勉強会を開催しました。勉強会では、平沼正二郎衆議院議員秘書の福井慎二氏が「皇室のご聖徳を仰ぐ」と題して講演しました。昭和100年、終戦80年の節目に皇室や英霊について振り返るべく、講演要旨を紹介します。
6面 天録時評 「教育基本法の目標に沿う教育振興基本計画を
施策評価も具体的な基準や
方法の明記が不可欠」
教育基本法が改正されて19年が経ちます。この間、国や地方自治体は教育基本法に掲げられた「教育振興基本計画」を策定し、教育活動を行ってきました。しかし、その実態は「道徳心を培う」や「わが国の郷土を愛する」などの教育基本法の目標が十分に反映されているとは言い難いものです。また、教育施策の評価についても評価基準や方法が明示されておらず不十分です。国民に教育基本法改正の意義を広めるためにも、評価の基準と結果を公表すべきです。
2面 巷 露 「落ち続ける月」
7面 天録時評 「火葬場増設で『火葬待ち』改善を
成功例を基に住民の理解促進が不可欠」
役立つ最新用語81
「避難所の生活環境を保持する
『スフィア基準』」
8面 日本の肖像122 帝国軍人の模範となる
乃木希典(中)
「己に対して一点の非も許さず、
修行者の人生を送る」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2056号 編集便りNo.467 2025/01/17
選択的夫婦別姓制度の導入を巡り、小中学生のほぼ半数が「家族で名字が変わるのは反対」と考えているという調査結果が産経新聞社のWEBニュースで配信されていました。将来、自分が結婚した際の別姓も「したくない」との回答も6割にのぼっていました。立憲民主党が選択的夫婦別姓制度の導入に関する法案を準備しているようですが、次世代を担う子供のことを考えれば、一部の大人の都合だけを優先して法改正をすべきではありません。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「選択的夫婦別姓制度はわが国の文化を破壊
新年になり、政治の動きで最も懸念されるのは、やはり選択的夫婦別姓に関する動向です。衆議院の法務委員長ポストを獲得した立憲民主党は、党機関紙で「党がリーダーシップをとって導入のための民法改正案を提出し、同法の制定を一番の目標にする」と息巻いています。改めて選択的夫婦別姓制度の問題点を指摘し、現実的な選択肢としての旧姓の通称使用を推進する法整備の必要性を訴えます。
(YouTube解説動画のURL)→ https://youtu.be/m2WLHDbpvEA
2面 天録時評 「習近平独裁から集団指導体制へ
わが国の新聞やテレビ報道は、米国については大統領選を巡る様々な権力闘争や不祥事などを詳細に報じますが、中国については中国共産党の公式発表などを報じるのがほとんどです。習近平独裁体制の終焉が指摘される中、中国共産党の隠蔽に協力する報道姿勢を改めるべきです。
3面 天録時評 「出入国管理政策
全世界で難民は増え続け、昨年4月で1億2千万人に達していますが、その解決の糸口さえ見えていません。昨年末のドイツのクリスマスマーケットでの惨事は難民問題の難しさを浮き彫りにし、人道的見地からの受け入れだけではよい結果をもたらさないこともあることが分かります。わが国の安寧を守る観点から、出入国管理政策を考えなければなりません。
4.5面 天録時評「次期エネルギー基本計画の原案を見る!
わが国のエネルギー政策の方向性を示す第七次の「エネルギー基本計画」の原案が、昨年末、経済産業省から示されました。国民からの意見聴取を経て、2月の閣議決定を目指しています。そこで、昨年本紙で連載した「エネルギー基本計画の改定に向けて」の中で示した論点を基に原案を総評してみます。
6面 天録時評 「家族崩壊を招く同性婚を認めるな
結婚制度は男女が家族を形成し、先祖からいただいた命を次世代に繋ぐため子供を産み、育てていくことを社会的に保護するための制度です。互いの利益の為だけにする同性婚を認めれば、先祖に感謝し子孫に責任を持つという婚姻制度の持つ役割が希薄化し、家族崩壊を助長させてしまいます。同性婚を法律で認めるべきではありません。
2面 巷 露 「政策立案能力の向上を」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「選択的夫婦別姓制度はわが国の文化を破壊
通称使用の法制化こそ民意に応える選択」
新年になり、政治の動きで最も懸念されるのは、やはり選択的夫婦別姓に関する動向です。衆議院の法務委員長ポストを獲得した立憲民主党は、党機関紙で「党がリーダーシップをとって導入のための民法改正案を提出し、同法の制定を一番の目標にする」と息巻いています。改めて選択的夫婦別姓制度の問題点を指摘し、現実的な選択肢としての旧姓の通称使用を推進する法整備の必要性を訴えます。(YouTube解説動画のURL)→ https://youtu.be/m2WLHDbpvEA
2面 天録時評 「習近平独裁から集団指導体制へ
中国共産党の権力闘争を報じないマスコミ」
わが国の新聞やテレビ報道は、米国については大統領選を巡る様々な権力闘争や不祥事などを詳細に報じますが、中国については中国共産党の公式発表などを報じるのがほとんどです。習近平独裁体制の終焉が指摘される中、中国共産党の隠蔽に協力する報道姿勢を改めるべきです。
3面 天録時評 「出入国管理政策
人道的見地だけでは難しい難民救済
国民の安寧を守る視点も重要」
全世界で難民は増え続け、昨年4月で1億2千万人に達していますが、その解決の糸口さえ見えていません。昨年末のドイツのクリスマスマーケットでの惨事は難民問題の難しさを浮き彫りにし、人道的見地からの受け入れだけではよい結果をもたらさないこともあることが分かります。わが国の安寧を守る観点から、出入国管理政策を考えなければなりません。
4.5面 天録時評「次期エネルギー基本計画の原案を見る!
評価できる原子力『最大限活用』の明記
再エネの主力電源化には不安も」
わが国のエネルギー政策の方向性を示す第七次の「エネルギー基本計画」の原案が、昨年末、経済産業省から示されました。国民からの意見聴取を経て、2月の閣議決定を目指しています。そこで、昨年本紙で連載した「エネルギー基本計画の改定に向けて」の中で示した論点を基に原案を総評してみます。
6面 天録時評 「家族崩壊を招く同性婚を認めるな
婚姻制度は子供の健全育成に不可欠」
結婚制度は男女が家族を形成し、先祖からいただいた命を次世代に繋ぐため子供を産み、育てていくことを社会的に保護するための制度です。互いの利益の為だけにする同性婚を認めれば、先祖に感謝し子孫に責任を持つという婚姻制度の持つ役割が希薄化し、家族崩壊を助長させてしまいます。同性婚を法律で認めるべきではありません。
2面 巷 露 「政策立案能力の向上を」
児相職員の資質向上も課題」
7面 天録時評 「便利だが危険なSNS
情報リテラシーを身に着ける努力を」
役立つ最新用語80
「氾濫する情報から身を守る『情報的健康』」
8面 日本の肖像121 帝国軍人の模範となる
乃木希典(上)
「虚弱体質の少年が愚直一直線、
軍人として人生の活路を開く」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
日本時事評論第2055号 編集便りNo.466 2025/01/03
明けましておめでとうございます。今年は、わが国の人口の約5人に1人が後期高齢者となり、年金、医療、介護の負担が急増し、社会保障費の増大への対策が課題になってきます。経済においても、昨年から続く物価上昇や円安の影響を受け、経済政策の見直しが求められます。こうした中、わが国は、少数与党で政権運営は綱渡り状態です。混沌とする社会情勢の中、『日本時事評論』では、様々な重要課題の解決に役立つ、未来への指針となる情報発信に一層努めて参ります。それでは紙面案内です。(田村)
1面 天録時評 「令和七年『乙巳』に因んで
国際的な秩序やルールを変えようとする勢力が拡大し、屋台骨も大きく軋んでおり、平和や豊かさを守る国政の舵取りは困難さを増すばかりです。目先の利害にとらわれず、一致団結する国民の忍耐力や協調性が求められます。今年の干支からこの一年を展望します。
2面 天録時評 「米を食べて食料安保に協力を
わが国は瑞々しい稲穂がめでたく実る「瑞穂の国」と称しています。ところが現状は、農業就業者の高齢化と後継者不足で耕作放棄地が急増し、農業の衰退が著しいのが実情です。農業は、生命維持に不可欠な食料を提供し、国土、環境を守り、多様な生物を育み、伝統・文化の基盤でもあります。農業再生の第一歩として、米飯中心の食生活に国民一人ひとりが取り組もうではありませんか。
3面 天録時評 「投票率向上のためにも『租税支出の透明化』を
政治への国民の信頼を回復するためには政治資金の透明化も重要ですが、国民の政治への関心を高め、政治参加を促すためにも税金の使い道を国民に分かりやすくする「租税支出の透明性向上」も不可欠です。しかし、わが国では租税支出の透明性は世界94位との調査結果もあります。税の使い道の透明性を高め、政策評価を公表することで、国民に税の使い道を分かりやすく示すことが国政の投票率向上にも必要です。
4面 天録時評 「島根原子力2号機の再稼働から考える
中国電力の島根原子力発電所2号機の原子炉が、今年1月10日から営業運転を始めます。再稼働まで約13年かかりました。原子力発電所の運転は「安全第一」が大前提であることは言うまでもありませんが、時間がかかり過ぎたことは否めません。国民全体の利益を図る観点から、原子力規制委員会の人材拡充などにより、安全審査における機動的な運用ができるように見直しが必要です。
2面 巷 露 「人間の不確かな理性」
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!
※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。
1面 天録時評 「令和七年『乙巳』に因んで
軋む国際秩序が国政の舵取りを困難に
柔軟性や協調性を発揮して乗り越えよう」
国際的な秩序やルールを変えようとする勢力が拡大し、屋台骨も大きく軋んでおり、平和や豊かさを守る国政の舵取りは困難さを増すばかりです。目先の利害にとらわれず、一致団結する国民の忍耐力や協調性が求められます。今年の干支からこの一年を展望します。
2面 天録時評 「米を食べて食料安保に協力を
健康維持のためにもお薦め」
わが国は瑞々しい稲穂がめでたく実る「瑞穂の国」と称しています。ところが現状は、農業就業者の高齢化と後継者不足で耕作放棄地が急増し、農業の衰退が著しいのが実情です。農業は、生命維持に不可欠な食料を提供し、国土、環境を守り、多様な生物を育み、伝統・文化の基盤でもあります。農業再生の第一歩として、米飯中心の食生活に国民一人ひとりが取り組もうではありませんか。
3面 天録時評 「投票率向上のためにも『租税支出の透明化』を
わが国の透明性は世界最低水準の94位」
政治への国民の信頼を回復するためには政治資金の透明化も重要ですが、国民の政治への関心を高め、政治参加を促すためにも税金の使い道を国民に分かりやすくする「租税支出の透明性向上」も不可欠です。しかし、わが国では租税支出の透明性は世界94位との調査結果もあります。税の使い道の透明性を高め、政策評価を公表することで、国民に税の使い道を分かりやすく示すことが国政の投票率向上にも必要です。
4面 天録時評 「島根原子力2号機の再稼働から考える
時間がかかりすぎる安全審査
規制委員会の機動的運用に期待」
中国電力の島根原子力発電所2号機の原子炉が、今年1月10日から営業運転を始めます。再稼働まで約13年かかりました。原子力発電所の運転は「安全第一」が大前提であることは言うまでもありませんが、時間がかかり過ぎたことは否めません。国民全体の利益を図る観点から、原子力規制委員会の人材拡充などにより、安全審査における機動的な運用ができるように見直しが必要です。
2面 巷 露 「人間の不確かな理性」
5面 天録時評 「最終処分地選定問題
概要調査の受け入れで国民的議論を高めよう
北海道知事は国益と科学に基づき判断を!」
6面 天録時評 「里親への養育支援の強化を
児相職員の資質向上も課題」
7面 天録時評 「太陽光パネル廃棄問題
リサイクル技術の確立と処理施設の建設を
不法投棄などの不適切処分を防げ」
役立つ最新用語79
「宇宙領域の安全保障『在日米宇宙軍』」
8面 日本の肖像120 近代的軍事制度の創立者
山縣有朋(補)
「常備軍の創設後、伊藤博文と共に
日本流近代国家建設に励む」
歴史家 鈴木旭
※皆様のご意見・情報提供(教育現場の声、地域の話題など)を編集部までお寄せください!!※編集便りのメール配信をご希望の方は、jijihyoron-3@river.ocn.ne.jp(編集部:田村)までご連絡ください。